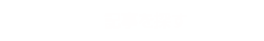【韓国昔話40】沈清伝6「盲人の宴に行く道のり」
王妃になった沈清は、きらびやかな服を着て、おいしい食べ物を食べながら、ありとあらゆる贅沢を享受しました。
しかし、一日として、父である沈盲人のことを忘れたことはありませんでした。
「お父さんは、今、どのような暮らしをしているだろうか。目は見えるようになっただろうか。もしや、すでにこの世を去ったのではないだろうか」
沈清には、心の休まる日がありませんでした。
人を遣わして調べることもできませんでした。王様をあざむいていたことが分かれば、それも大変なことです。
悩んでいた沈清は、ある知恵をしぼりだしました。
「王様、民の中で、目の見えない盲人たちの立場をお考えになったことがありますか」
「突然、なぜそのようなことを聞くのですか」
「この美しい宮殿で暮らしていると、ふと盲人たちがかわいそうだという考えが浮かんだのです」
「もちろん盲人たちはかわいそうでしょう。しかし、どうするというのです。いくら王でも、彼らの目を開かせることはできないが」
「盲人たちを宮殿に呼んで、慰労の宴でも催してあげればいかがでしょうか」
「うむ、それは良い考えです。王妃の温かい心は、本当にすべての民の母にふさわしい」
王妃の憂いを知っていた王様は、こころよく承諾しました。
このようにして、ひと月の間、宮殿の中で盲人たちのための宴が開かれることになりました。
盲人たちを呼び集めるようにという命令が国じゅうの郡の役所に送られました。
「このたびの宴は、慈しみ深い王妃が哀れな盲人たちを慰労するために設けられたものである。この国の盲人たちは、男であれ女であれ、老人はもちろん、幼い子供に至るまで、一人も漏らさずにすべて参席させるように。もし一人の盲人でも漏らせば、その郡の郡守には大きな罰が下されるだろう」
沈盲人とペンドク母さんも、宴に参席するために出発しました。
ペンドク母さんが荷物を頭に載せて前を歩き、沈盲人はふろしき包みを背負って後ろにつづきました。
ペンドク母さんは、沈盲人の杖の先をつかんで歩きながら歌を歌いました。
「なぜ行くのだろ、なぜ行くのだろ、ソウルまでの遠い遠い道のりを、輿もなしになぜ行くのだろ」
もう片方の端を握ってあとに従っていた沈盲人が、その歌を引き継ぎました。
「なぜ行くのだろ、なぜ行くのだろ、ソウルまでの遠い遠い道のりを、目の見えない道のりをなぜ行くのだろ」
二人は、足が痛くなれば涼しい木陰で休み、のどがかわけば小川の水をすくって飲みながら、ひたすら歩きつづけました。野を越えて、山を越えて、村を横切って歩いていきました。
行く先々では、自分たちと同じように宴を訪ねていく盲人たちにたびたび出会いました。
ある日、日が暮れかけたとき、ソウルに向かっていた盲人たちが宿の中に入っていくのを見たペンドク母さんが、沈盲人の腕をつかんで引っ張りました。
「足も痛いし、お腹も空いて、もうこれ以上、きょうは歩けません。今晩はここで寝ましょう」
「旅費がいくらも残っていないので、どこか人の家の軒下で休みましょう」
「いやです。私はここで楽に休んでから行きたいのです」
ペンドク母さんがあまりにもせがむので、沈盲人は、仕方なく宿に入っていきました。
翌朝、目を覚ました沈盲人は、
「あなた、さあ出発する準備をしましょう」
と声をかけました。
ところが、どうしたことか、ペンドク母さんの気配はありませんでした。
隣の布団をさぐってみた沈盲人は、縁側に出ていって大きな声で妻を呼んでみました。
「女房や! 女房や!」
すると、宿の主人がやってきて言いました。
「お宅の奥様は、朝早く出発しましたよ」
「出発したって、わしを置いてどこに出発したというのですか」
「それは、私が知るはずがないでしょう。若くてお金が少しあるように見える黄盲人と二人で、逃げるように出ていきましたよ」
「何だって? 私の女房が、ほかの男と一緒に逃げていったというのですか」
「様子からして、逃げていったに違いありません。もうかなり遠くに行ったはずですよ」
沈盲人は、その場にぺたりと座り込んでしまいました。
「アイゴー、ペンドクなしに、どうやってソウルまで行き、何を楽しみに生きていけばいいのか」
沈盲人は、胸をたたいてわっと泣き出しました。
沈盲人は、涙をほろりとこぼし、鼻水をぐすんとすすり上げながら身の上をなげき、愚痴をこぼしました。
「アイゴー、悪いやつめ! 甘い汁だけ吸って、ありとあらゆる愛嬌をふりまいておきながら、履き尽くしたわらじを捨てるように、わしを置いてどこに行った? お金もなければ、目も見えなくて、お先真っ暗だ!」
ひとしきり嘆息と恨み言を並べ立てていた沈盲人は、ようやく気を取り直して立ち上がりました。
「ソウルまでの道のりは遠く険しいが、一人でも行かなければならない。宮殿の宴には食べたり飲んだりする食べ物がたっぷりあるというのに、食べずに死ねば、悔いばかりが残る」
沈盲人は、ふろしき包みを担いで、たどたどしく宿を出ました。
転んだり塀にぶつかったりしながらも、沈盲人は、ソウルへの道のりをあきらめませんでした。
歩いている途中で、人の気配がすれば、
「こちらに行けば、ソウルですか?」
とたずねました。
このように旅を続けていると、なかなか進まず、次第に季節は春から夏へと移っていきました。
ある日、汗をだらだら流しながら道を歩いていた沈盲人は、小川が流れる音を聞き、
「お腹が空いて、のどがかわいたので、水でもたっぷり飲んでいこう」
と、小川のほとりに下りていきました。
川の水で、のどの渇きと空腹をまぎらわせた沈盲人は、
「えい、どうせなら暑さも冷ましていこう」
と言って服を脱ぎはじめました。ちょうど道を行き交う人もいませんでした。
「いやあ、気持ちいい!」
沈盲人は、川の水に体をつけたまま、いい気分で鼻歌を歌いはじめました。
そこを通りがかった村の子供たちが、小川のほとりにある沈盲人の服を目にしました。
「おいみんな、ちょっといたずらをしてやろう」
「よし、やろう、やろう」
子供たちは、沈盲人の服と荷物をこっそりひろって村に逃げていきました。
何も知らない沈盲人は、足をばたつかせながら暑さを冷ましていました。
「もうそろそろあがることにするか」
沈盲人は、たどたどしい手つきで、川のほとりに置いたはずの服に手を伸ばしました。しかし、いくら腕を動かしても、手には何もひっかかりませんでした。
「誰がわしの服を持っていったのだろう?」
近くの草むらまではいあがって、しばらく服を探していた沈盲人は、とうとう泣きべそをかいてしまいました。
「これは大変なことになった。体にまとう服がなくて、どうやって歩いたらいいのだろう」
沈盲人は、真っ裸の下半身を帽子で隠して立ち上がりました。幸い、子供たちは帽子までは持っていきませんでした。
どこかに行って古着でももらおうと思い、たどたどしく歩いている沈盲人を見て、とおりがかった農夫がくすくすと笑いました。
「もしもし、盲人のお方。いくら盲人でも裸で歩いてまわるとは、気は確かですか?」
「どなたか知りませんが、私の事情を少し聞いてください」
沈盲人は、服を盗まれた事情を話し、助けを請いました。
「子供たちのいたずらでしょう。もう少し行けば、精米所がありますが、子供たちがそこに集まって笑っていましたよ。そこに行ってみてください」
沈盲人は、精米所に訪ねていきました。
精米所では、ちょうど村のおばさんたちが麦をついているところでした。
「あらまあ、えげつない!」
「おへその下に帽子をかぶるとは。ほほほっ」
村のおばさんたちは、沈盲人を見て笑いました。
「もしもし、おばさんがた。人をからかわないで、わしの服を探してください」
沈盲人がお願いすると、おばさんたちは互いに目配せをして、温情を示すかのように言いました。
「代わりに、臼をついて、私たちの麦を精白してくれますか」
「先に服を探してくれれば、臼をついてさしあげます」
「分かりました。約束は守らなければなりませんよ」
おばさんたちは、精米所の片隅に集まってくすくす笑っていた子供たちから沈盲人の服と荷物を取り上げて、沈盲人に渡しました。
服を着た沈盲人は、約束どおり、臼をつきはじめました。
ごっとん、ごっとんと踏み臼を踏み、すっとん、すっとんとつき臼をつきました。
つづく