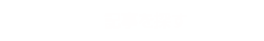【韓国昔話40】沈清伝5「ペンドク母さん」
いっぽう、愛する娘を死の道へと行かせてしまった沈盲人は、涙の歳月を過ごしていました。
「かわいそうな私の娘、清よ! この愚かな父を許してくれ」
沈盲人は、寝てもすすり泣き、覚めてもすすり泣きました。
村の人々は、沈清の孝心をたたえるために、村の入口に孝行碑をたてました。孝女沈清のことを刻んだ石碑です。
沈盲人は、清を思い出すたびに、杖をたよりに訪ねていっては、その石碑をなでました。
「清よ、また来たよ。おまえは父の目を開かせようと溺れ死んだが、わたしは今なお目を開くことができないまま、しぶとく命をつないでいるよ。こんなことなら、いっそわしをあの世に連れていってくれ」
このように言いながら石碑をなでて涙を落としつづけたので、石碑のかわく日がありませんでした。それで、人々は、この石碑を堕涙碑(涙を流す石碑)と呼びました。
このころ、沈盲人の家から近い所に住んでいるペンドク母さんという未亡人がいました。ペンドク母さんは容姿からしてとても醜い人でした。
すいていない髪の毛は、逆立って馬のたてがみのようであり、額は、ひょうたんの器のようにぽこんと突き出ていました。
目は、骸骨のようにぼこんとくぼんでいて、鼻は、ゆずの皮のようにでこぼこなだんご鼻、頬は、味噌玉こうじのように垂れ下がっていました。
あごは、しゃもじのようであり、歯は、先のとがったのこぎり歯で、手は、釜のふたのように大きく荒々しい手をしていました。
腰はうすのようで、腹は太鼓腹で、お尻は平べったく垂れ下がっていました。
手と足のつめは、垢がたまって真っ黒で、むしろのような履物をずるずる引きずってよたよた歩く姿は、まるで太ったブタのようでした。
見た目が醜くても、心だけでもきれいならよいのですが、ペンドク母さんは、行動も性格もどうしようもなく悪い人でした。
一日中寝てばかりいて、夜になると、あちこち歩いてまわりながら、おせっかいをしていました。
どこかの家の婚姻話が持ち上がるとすぐに悪いうわさを広めたり、人の家の戸口に口をあてて「火事だ!」と叫んで逃げたり、通り過ぎる人の後ろで悪口を言ってけなしたり、隣同士のけんかをけしかけたりなど、悪いことは一手に引き受けてまわりました。
そればかりでしょうか。寝るときは、ぎりぎりと身の毛もよだつような音を立てて歯をきしませ、突然起き上がって「ああ、ああ!」と泣き叫ぶ癖までありました。
村の人々がペンドク母さんを見て、
「ちらりと見ればじろりと見て、じろりと見ればちらりと見る。憎たらしいペンドク母さん」
と悪口を言いました。
ところで、ある日、ペンドク母さんは次のような話を耳にしました。
「沈盲人は、ああ見えても、けっこうなお金持ちだそうだ。沈清が物ごいをして集めた穀物もかなりあるし、船乗りたちが哀れに思って沈盲人にあげていったお金もかなりの額になるそうだ」
ペンドク母さんは、その話に興味を抱き、そのまま沈盲人を訪ねていきました。
「いたずらに娘だけを失って、目は見えないとは。まったく仏様も役に立たないねえ」
ペンドク母さんは、哀れな沈盲人を助けてあげましょうといって、沈盲人の機嫌を取りました。
「どんなに寂しくつらいですか。私があなたの手足になってさしあげればどうですか」
沈盲人は、ペンドク母さんの顔かたちを見ることができませんでした。また、ペンドク母さんの行動についても聞いたことがありませんでした。
それで、ペンドク母さんが鼻声交じりでこびると、
「このように美しい心を持った女性がわたしを助けてくれるとは、なんと幸いなことか」
と満足に思いました。
そうこうするうちに歳月が流れ、娘の清に対する悲しみが少し和らぐようになると、沈盲人は、ついにペンドク母さんを家に迎えて一緒に暮らすようになりました。
新しい妻として迎えたペンドク母さんは、沈盲人にとって、やさしく、美しくて、ありがたいばかりでした。
「あなた、あなたの健康のためにめんどりで料理をこしらえたので、召し上がってください」
ペンドク母さんは、にわとりを料理したり、たびたびモチやハチミツを買って食べたりしながら、すべて夫のためであると言いました。
あるとき、アンズの実をひとかご買って、こっそり一人でむしゃむしゃ食べていると、沈盲人が
「何をそのようにむしゃむしゃ食べているのですか?」
と尋ねました。
ペンドク母さんは、すぐにうまく言いつくろいました。
「ちかごろ、なぜかすっぱいものが食べたくてアンズの実を食べていたのです」
「それでは、もしや赤ん坊を身ごもったのではないですか」
「そうですね。そのような気もするし、そうでない気もするし‥‥」
「間違いなく妊娠です。すっぱいものでも何でも、食べたいものはすべて買って食べなさい」
沈盲人は、新しい妻が妊娠したと思って喜びました。
このようにして数か月が過ぎると、沈盲人の財産はほとんど底をついてしまいました。
ようやくそれに気づいた沈盲人は、一人なげいてため息をつきました。
「今まであった財産がつきるとは‥‥。私の娘、清の命と引き換えに得た財産なのに、それをすべてなくしてしまったとは!」
外から帰ってきたペンドク母さんは、この言葉を聞いて、ぷんぷんと腹を立てました。
「あなた、今、財産がなくなった罪を私にかぶせようとしているのですか? 目の見えない老人のために、モチだの酒だのと、真心を込めて面倒をみてあげたのに、今になって身代をつぶしてしまったどろぼうにしようとしているのですか!」
「どろうぼうにするなんで、だれがそのようなことを言いましたか」
「ああ、なんて運命だ! くやしくて悲しくて、どうすればいいの? 私一人で食べたならくやしくはないだろうが、老人のために尽くしてあげた真心はすべてむだだった。ああ、なんて運命だ」
ペンドク母さんは、床をどんどんたたきながら、声をあげて泣きじゃくりました。
あわてふためいたのは沈盲人でした。新しい妻が家から出て行ってしまったら大変だと思い、
「私が悪かった。これから生きていくことを心配しただけであって、つめの垢ほども、あなたのせいにしたつもりはない」
と言ってひたすらあやまりつづけました。
ペンドク母さんは、泣くのをやめ、怒りをおさめるふりをしました。
しかし、そのときからは、いつ沈盲人を捨てて逃げていこうかと思案を巡らせはじめました。
ある日、郡の役所から、「急いで来るように」という伝言が沈盲人のもとにとどきました。
「役所がどうして私を呼んでいるのだろう? もしや娘を売り飛ばした罰を今になって与えようとしているのではあるまいか」
沈盲人は、不安げな面持ちで郡の役所に行きました。
「よし、機会は今だ!」
ペンドク母さんは、米やら衣類やら、家の中のものをありったけ引っ張り出してきて荷造りを始めました。
逃げ出そうという魂胆でした。
ところで、米びつの底に少し残った米をそのまま置いていくのはもったいないと思いました。
ペンドク母さんは、その米を引っかいてきれいに集め、居酒屋でお酒と交換してきました。そして、どんぶり一杯のお酒をごくごくと飲みほしました。
酒に酔ったペンドク母さんは、そのまま縁側にごろんと横たわり、ぐうぐうといびきをかきはじめました。
いい気持ちで寝ていたペンドク母さんを、郡の役所から帰ってきた沈盲人が揺り起こしました。
「あれ、郡の役所でたたかれて、のそのそはって帰ってくるものと思っていたのに、何をにこにこしているのですか」
ペンドク母さんは、首をかしげてたずねました。沈盲人に内緒で逃げ出そうとしていたことがばれるのではないかと思い、心配しましたが、意外にも沈盲人の顔は明るく輝いていました。
「たたかれるどころか、良いことばかりが起きたのだよ」
「それはどういうことですか」
「この国の王妃様にとても善良な方がつかれたという知らせは、あなたも知っているでしょう?」
「もちろんです。私のように顔もきれいで、心も善良な王妃様だそうですね」
「ほっほっ、それは分からないだろう。ところで、その王妃様が、国じゅうの盲人たちをすべて宮殿に呼び集め、大きな宴を催されるというのだよ」
「はい? 大きな宴ですか」
「そうです。都まで行き来する旅費まで下さるそうだ。あなたも一緒に行くので、すぐに荷物をまとめなさい」
ペンドク母さんは、沈盲人が眠りについたら逃げ出そうと思っていました。しかし、沈盲人の話を聞いてみると、今夜逃げる理由がなくなりました。
「旅費までくれるのなら、それまで奪って逃げなくては!」
このように考えたペンドク母さんは、しらばくれて答えました。
「ほほほ、こんなこともあろうかと思って、すでに私が荷物をまとめておきましたよ」
「えっ、あなたには将来のことが分かる才能があったのですか」
「将来だけではありません。そのあとのことも分かりますよ」
つづく