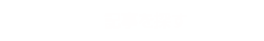【韓国昔話40】沈清伝4「花から出てきた仙女」
「あれは何だ? 花のようだが‥‥」
「どこだ、どこだ!」
船乗りたちが、がやがや騒ぎながら船の片側に集まってきました。
彼らは、三年前にこの印塘水に沈清をささげた、正にその船乗りたちでした。
彼らは、中国でお金をたくさん稼いだのち、その帰りに印塘水に立ち寄り、死んだ沈清の魂をなぐさめようと祭祀を執り行っていたところでした。
そのとき、静かな海の上に、何やら大きな一輪の花が浮かび上がってきたのです。
「初めて見る花だ!」
「とても大きいぞ!」
船を近くに寄せてみると、虹のようにきれいな花が強い香りを漂わせていました。今まで一度も見たことのない美しく大きな花でした。
「沈清の魂が花になったのだろうか」
「そうかも知れない」
船乗りたちは、花をすくいあげ、再び故郷への道を急ぎました。
陸に上がった船乗りたちは、王様を訪ねていき、この珍しい花をささげました。王様も、初めて見る大きく美しい花に感嘆しました。
王様は、船乗りたちから沈清の話を聞きました。そして、「その花には沈清の魂が宿っているはずです」という話を聞くと、またとなくその花が貴く思われました。
王様は、花を自分の部屋の近くの庭に植えるように命じました。
ある晩、王様は、一人で庭を散策しながら月をながめていました。
そのとき、花の香りがぷんと漂ったかと思うと、船乗りたちがささげたその花のつぼみがゆっくりと開きはじめました。
「花が真夜中につぼみを開くとは」
そう思って、花のつぼみのすぐ近くまで近寄った王様は、びっくりしてしまいました。
花のつぼみの中から、見知らぬ少女が眠りから覚めたように体を起こしたのです。
仙女のように美しいこの少女は、まさしく印塘水に身を投じた沈清でした。
三年前、水に飛び込んだ沈清には、「もう死ぬのだなあ!」という果てしない絶望だけがありました。
ところが、水の底に沈んだ沈清の目の前が突然ぱっと明るくなりました。そして、どこからか一台の華やかな花の輿が現れました。
花の輿をとりまいていた女性たちは、沈清を輿に乗せて言いました。
「私たちは、竜王様に仕えている竜宮の宮女たちです。竜王様があなたをご案内してくるようにと仰せになりました」
沈清は、花の輿に座り、水の中を見物しながら、とても大きく美しい竜宮に入っていきました。
竜宮に連れてこられた沈清に向かって、竜王様は言いました。
「善良で、この上なく孝心の厚い沈清よ、聞きなさい。天の神様がおまえの孝心に感動され、おまえを保護するようにと命じられた。ゆえに、ここで心安らかに過ごしなさい。時が来れば、人の世にもう一度送り返してあげよう」
このようにして沈清は、竜宮で暮らすようになりました。
竜王様が天の神様にお願いし、沈清は、顔も知らずに別れた母に、ほんの少しの間、会うこともできました。
三年が過ぎたとき、竜王様が言いました。
「もう一度、人の世に送り返してあげよう。そこで幸せに暮らしなさい」
「竜王様のご恩は決して忘れません」
別れのあいさつが終わると、竜王様は、沈清を花の中に入れました。そして、沈清の入っている花房を宮女たちが印塘水に持っていきました。
深い眠りに落ちて花のつぼみの中に横たわっていた沈清は、王様が庭を散策する足音に目を覚ましました。
夢かうつつかとまどっている沈清の目に一番初めにうつったのは王様の顔でした。
最初、王様はとても驚きましたが、すぐにやさしいほほえみを浮かべて尋ねました。
「驚かないでください。ここは宮殿で、私はこの国の王です。ところで、あなたはどなたで、どこから来たのですか」
沈清は驚き恐れましたが、すぐに心を落ち着けて
「私はたった今、深い眠りから覚めました。夢の中で、しばらく竜宮を見物してまわっただけですが、どうして花の中に横たわっていたのか、まったく理由が分かりません」
とうまく言いつくろいました。
「過去にどこでどのように暮らしていたかはそれほど重要なことではありません。ちょうど私は王妃になる人をさがしていたところですが、おそらくあなたは、天が私に与えてくださった仙女でしょう」
王様は、花の中の少女が、船乗りたちに聞いた沈清が再び生き返ったものと確信しました。しかし、わざと何も知らないふりをして
「私はとても孤独なので、王妃になってくれませんか」
と言って、手をさしのべました。
沈清が見ると、この若い王様は、顔立ちもうるわしく、心もやさしそうに見えました。
「この方の願いを断りたくない」
沈清は恥じらいながら手を差し出しました。
沈清の手をそっと握りしめた王様の手はとても温かい手でした。このようにして、五月五日、沈清は王様と婚礼をあげました。
目の見えない貧乏人の沈学奎の娘として生まれ、ご飯をもらって歩いていたこじきの少女沈清が、今は、国中の民の母である王妃になったのです。
すべての臣下と民が新しい王妃を祝福しました。
つづく