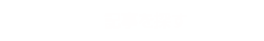【韓国昔話40】沈清伝7「見える、見える!」
沈清は、盲人の宴が始まると、今か今かと父を待ちつづけました。しかし、父が来たという知らせは一向に来ませんでした。
沈清は、宮殿に集まってくる盲人たちの名前と年齢、住所などを記した名簿を、毎日、くまなく調べてみました。
「きょうは、お父さんが来ただろうか」
胸をどきどきさせながら名簿を広げてみた沈清は、
「きょうも来なかった。どういうわけで、このように遅れているのだろうか」
と言って涙ぐみました。
ひと月の間の宴はほとんど終わろうとしているのに、「沈学奎」という名前を見つけることができなかった沈清は、
「もしや、お父さんは、もう目が見えるようになったので宴に来ないのだろうか」
と希望的なことを考えてみたりもしました。
ついに宴の最後の日になりました。
この日も、名簿にくまなく目を通してみましたが、父の名前は記されていませんでした。
日がだんだん暮れてくると、沈清はやきもきして居ても立ってもいられなくなりました。
「もう我慢できない、私が直接探してみよう」
沈清は、宴の開かれている広場に出てみました。
最終日からなのか、宴の開かれている広場は、大勢の盲人たちでごった返していました。
数百人の盲人たちががやがやと騒ぎ立てながら、料理を食べていました。
「こんなに大勢の盲人たちがいるのに、なぜお父さんはいないのだろう」
沈清は、広場を明るくするように告げたのち、盲人たちをひとり一人よく見てみました。
しかし、父である沈盲人と似ている人さえも目にとまりませんでした。
「いったいどうしたことだろう?」
いっぽう、ありとあらゆる苦労をしながら、沈盲人がどうにかこうにか宮殿の門の前にたどりついたのは、宴がちょうど終わるころでした。
宮殿の門を守っていた兵卒が近づいてきて、沈盲人を呼びとめました。
「もしもし、どこに行くのですか」
「盲人の宴に来た者です」
「なぜこんなに遅く来たのですか。宴はもう終わりですよ」
その言葉を聞いて、沈盲人はがっくりと肩を落とし、しばらくその場にぼうぜんと立ち尽くしました。やがて首をうなだれて宮殿に背を向けようとしました。
そのときです。
ちょうど門の前をとおりがかった役人が沈盲人に声をかけました。
「ちょっと待った! 王妃様は、宮殿に訪ねてくる盲人たちの名前を一人も漏らさないようにとおっしゃった。名前と住んでいる所を言ってみなさい」
「はい。私は、黄海の挑花洞から来た沈学奎と申します」
「沈学奎ですって? あー、あなたが本当に沈学奎なのですか。ついにお見えになった! さあ、早く私と一緒に入りましょう」
役人は、いきなり沈盲人の腕をつかんで歩きだしました。
「いや、どうしたことですか」
「高貴なお方が、沈学奎という盲人を探してくるようにとおっしゃったのです」
役人に引かれていきながら、沈学奎は次第に不安でいっぱいになりました。
「私が娘を売り飛ばした事実を知って、その高貴なお方が罰を下そうとしていらっしゃるのではあるまいか。そうなっても仕方がない。わしは天罰を受けて当然な罪人だから」
沈盲人は、がっくりと首をうなだれたまま、役人に引かれて宮殿の中に入っていきました。
やがて役人は、宮殿の奥まった場所に沈盲人を立たせ、年老いた内官(宮中の官僚)に引き渡しました。その内官は、王妃のお世話係りをしている人でした。
内官は、沈盲人の名前と住んでいる場所を根掘り葉掘り聞いたのち、
「王妃様があなたを今か今かとお待ちです」
と言って、内殿(王妃の起居する宮殿)に連れていきました。
宴の広場まで出ていっても父に会えなかった王妃、沈清はとても失望したまま、内殿に戻ってきました。
「やはり挑花洞に人を送って、お父さんの消息を調べてみなければならない」
沈清は、父に会えなかった切なさで涙を流しました。
このとき、内官が入ってきて言いました。
「王妃様、沈学奎というお方をお連れしてまいりました」
沈清は、びっくりしてすくっと立ち上がりました。
「何ですって?」
「沈学奎という盲人をお連れしてまいりました」
内官が、もう一度申し上げて横に退くと、そこには、内官に従って入ってきた盲人が床にひれ伏していました。
「桃花洞から来た沈学奎と申します」
その声は、遠い昔に聞いた父、沈盲人の声に間違いありませんでした。
「顔を上げてみてください」
沈盲人はゆっくりと顔を上げました。
「アイゴー、お父さん!」
沈清は、ひれ伏している父に駆け寄って両手をつかんで起こしました。涙が前をふさぎ、のどがつまって、次の言葉が出てきませんでした。
「いや、誰がわたしをお父さんと呼ぶのですか。わたしの娘は、もう三年前におぼれ死んでこの世にはいません」
沈盲人はびっくりして、沈清の手をふりはらいました。誰かが自分をからかっているのだと思ったのです。
沈清は、かまわず父の目をなでながら泣き叫びました。
「アイゴー、お父さん! 今も目が見えないのですね。印塘水の深い海に落ちて死んだ娘は、このように生きて戻ってきたのに、お父さんはどうして娘の顔も見ることができないのですか」
「印塘水に落ちて死んでから、生き返っただって?」
「はい、お父さん。私が清です。早く目を開いて娘の顔を少し見てください」
目の前に立っている人が娘だということを知った沈盲人は、驚いてどうすればよいか分かりませんでした。
「清だって? 私の清に間違いないというのか」
「はい、清です。私が清です」
「これは夢なのか現実なのか。夢ならば覚めないでくれ。現実ならば娘の顔を一度見てみよう! アイゴー、もどかしい! 目が開けば、娘の顔を見ることができるのだが‥‥」
沈盲人は、涙をぽろぽろこぼしながら悔しがりました。
沈清も、父の濡れた目をふいてあげながら、足を踏み鳴らしました。
「お父さん、私は、生き返って王妃になりました。ところが、お父さんは今もなお目を開くことができないので、どれほどもどかしいですか。もしお父さんの目を開くことさえできれば、何もかもすべて捨てて、もう一度この命をささげます」
「それはできないことだ。一度殺した娘をもう二度と殺すことはできない」
「それなら、早く目を開いてください。目を開いて娘を見てください」
「うん、清よ! すぐにでも目を開いておまえの顔を見てみたい。しかし、犯した罪が大きくて、今なお仏様が怒っていらっしゃるようだ。仏様、お許しください。この罪人が永遠に目を開けなかったとしても、私の娘だけは永遠に幸せに暮らせるように、どうぞ見守ってください」
沈盲人は、このように言いながら、娘の頬を両手でなでました。
「目で見ることはできなくても、手でおまえの顔を触ってみよう。おまえの顔を心の底に深く刻んでおこう」
このように言いながら、娘の鼻をさわり、唇をさわっていた沈盲人の目の前が、突然、ぼんやりと明るくなってきました。
そして、きらびやかな装いの王妃がすぐ目の前で泣いている姿が沈盲人の目に入りました。
沈盲人は、自分は夢を見ているのだと思いました。夢で、王妃になった娘と出会っているのだと思ったのです。
ところが、心を落ち着けてよく見てみると、それは夢ではありませんでした。
目の前で泣いている王妃は、若くして死んだ妻の姿に生き写しだったのです。
「アイゴー、清よ! 私の娘、清が見える! どうしておまえは、こんなにも母親に生き写しなのだ」
沈盲人は娘の手をしっかりつかみ、うれしくてどうすればよいのか分かりませんでした。
「お父さん、本当に目が見えるのですか。私が見えるのですか」
「もちろんだ、見えるとも、見えるとも! きらびやかな装いに、花のような顔、露のような涙まで、はっきりと見えるよ!」
「お父さん、目が見えるようになったのですね。この娘を見たくて目が見えるようになったのですね!」
沈清は、あまりにうれしくて、父を抱き締めたままぐるぐると回りました。王妃の体面も忘れたまま、子供のようにピョンピョンはねながら喜びました。
「奇跡」という言葉があります。
人の力では到底成し遂げられないことが起こることを「奇跡」と言います。この日、沈盲人は奇跡のように目が見えるようになりました。
仏様の恵みでしょうか。それとも、娘を一度見てみたいという父の切なる願いにまぶたが開いたのでしょうか。あるいは、沈清の深い孝心に、天の神様も感動されたのでしょうか。
いずれにせよ、沈盲人は目が見え、愛する娘の姿をはっきりと見ることができるようになりました。
ところで、まさにこの時間、もう一つの奇跡が起こりました。
宴に参席していたすべての盲人たちの目が、あっという間にぱっと開くようになったのです。
目を開いた盲人たちの喜びをどうやってすべて説明することができるでしょうか。
盲人たちは、うれしくて感激して、おんおん泣いたり、ひょいひょいと踊り始めたり、もうどうすればよいのか分かりませんでした。
ところで、不思議なことに、ペンドク母さんを誘惑して一緒に逃げてきた黄盲人は、片方の目だけが開きました。
ちょうど猟師が鉄砲を撃つときのように、片方の目だけが開いたのです。それでも、黄盲人はうれしくて、ひょいひょいと踊りを踊りました。
いっぽう、ペンドク母さんはどうなったでしょうか。
黄盲人と逃げてきたペンドク母さんは、ある日の晩、
「一生、盲人の女房として暮らすことはできない」
と思い、黄盲人の荷物をごそごそと探り、お金の包みを盗んで、こっそり逃げていってしまいました。
しかし、いくらも行かずに強盗に出遭い、お金の包みをすっかりまきあげられたのち、いやというほど殴られました。
無一文の乞食になってあちらこちらをさまよっていたペンドク母さんは、沈盲人のうわさを聞きました。
印塘水に落ちて死んだ沈清が生き返って王妃になり、沈盲人は目が開いて、王妃と一緒に暮らすようになったといううわさです。
「アイゴー、私がばかだった。このようになることが分かっていれば、沈盲人の面倒を最後まで見ていたのに。そうすれば、私も宮殿で贅沢にくらしていたはずなのに。アイゴー、悔しい。転がり込んできた福をけとばしてしまった!」
ペンドク母さんは、残念で悔しくて、大声をあげて泣きながらどこかに去っていってしまいました。
その後、ペンドク母さんを見た人は誰もいないそうです。
おわり