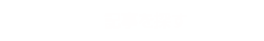【韓国昔話40】沈清伝3「約束」
沈盲人は、娘がなかなか帰ってこないので、とても心配になりました。
「清に何かあったのだろうか? なぜまだ帰ってこないのだろう?」
沈盲人は居ても立っても入られず、部屋の戸を大きく開いたまま、風の音を聞いただけでも
「清はまだか?」
と言って、お尻を上げたり下ろしたりしました。しかし、一向に、娘は帰ってきませんでした。
「だめだ、こうしてはいられない」
沈盲人は、杖をついてふらふらした足どりで外に出ました。
しかし、久しぶりに外に出てみると、以前は、清が引っ張ってくれた杖にたよって上手に通っていた道も、杖だけでは全く方向感覚がつかめませんでした。
沈盲人は、川の土手道の所まで来ると、さらにてんてこまいしてしまいました。
そして、土手道でうろうろしていると、うっかり足をふみはずし、沈盲人は土手下に転がっていって、そのままどぶんと川に落ちてしまいました。
「あっぷ、あっぷ、誰か助けてくれ!」
沈盲人がもがいていると、ちょうど近くを通りがかった夢恩寺のお坊さんがかけつけつけてくれました。
お坊さんは、沈盲人を助けてあげたのち、はあはあと荒い息をしている沈盲人の姿を見てつぶやきました。
「まったく気の毒なことだ。わたしの寺の仏様に供米三百石をささげさえすれば、目はぱっと開くのだが‥‥」
沈盲人は、はっと耳をそばだてました。
「もしもし、お坊様。仏様に米をおささげすれば目が見えるようになるという言葉は本当ですか」
「もちろんです。仏に仕える僧がどうして偽りを申しましょう」
沈盲人は、すぐにでも供米をささげて目が見えるようになりたいと思いました。しかし、米三百石はおろか、一握りの米もささげられない身の上でした。
「お坊様、供米をささげるという約束で名前から先に書いておき、供米はあとからささげてはいけませんか」
「仏様との約束を破れば、大きな罰を受けるようになりますよ」
「約束は必ず守りますので、名前から先に書いてくださいませ」
沈盲人は、目が見えるようになりたいという一心で、後先を考えないで、お坊さんがもっている布施帳に自分の名前を書いてもらい、その横に「供米三百石」と書かせました。
家に帰ってきた沈盲人は、とんでもないことをしたと思って、とても心配しました。
「どうしよう? 守れもしない約束をして、あとで、どうやってその罰を受けようか?」
沈盲人は、胸を打ちながら悔やんで、また悔やみました。
やがて、誕生日のお祝いの家からおいしい食べ物をたくさんもらってきた沈清が帰ってきました。
沈盲人は、沈清を見るなり
「ああ、清よ、大変なことになった。もうこの父は、足のなえた人か、そうでなければ大蛇になる運命だ」
と言って、涙をぽろぽろと流しました。
「お父さん、どうしたのですか」
沈清が尋ねると、沈盲人は、仏様との約束について話しました。
「お父さん、あまり心配しないでください。天が崩れても、はいでる穴はあると言いますから、きっと何かよい方法があるでしょう」
沈清は、そう言って父をなぐさめました。しかし、これといった方法はなかったので、沈清もまた心配するようになりました。
翌日、沈清は、裏庭に行って、井華水(早朝最初にくんだ井戸水)をかめ置き場に置いて祈りました。
「お願いします、お願いします。天と星と月と地の上のすべての神様にお願いします。一つしかない私の体をささげてでも、お父さんの目が見えるようにしてください」
沈清は、夜ごとに祈り、また祈りました。
このような精誠に天が感動したからでしょうか。
精誠をささげてから四十日目の日、沈清は、ほかの家の仕事を手伝って帰ってくる途中で、村の人々がひそひそと話している声を耳にしました。
「遠くから来た船乗りたちが、供え物に使うということで、お金で買える十五歳くらいの娘をさがしているそうだ」
「本当か? しかし、いくらお金がほしいからといって、人を売ったりする人がいるだろうか」
沈清がじっと聞いてみると、船乗りたちのさがしている人は正に自分であると思いました。
「天が私を助けてくださったのだ!」
沈清は、父には内緒で、船乗りたちをたずねていきました。
「十五歳ぐらいの娘を買って、何に使うのですか」
「我々は、遠い中国まで海を渡って商売をしている船乗りだ。海を渡っていくと印塘水とう場所があるのだが、そこには竜王様がすんでいるという言い伝えがあって、我々は、船路の旅が無事であるように、数年に一度ずつ、その竜王様に美しい娘をささげているのだ。そして、ちょうど今年が娘をささげなければならない年なのだ」
「それでは、私を買ってください。今年で十五歳です」
沈清は、米三百石が必要な哀れな事情を話しました。
「ははあ、この村にこのような孝女がいたとは! よろしい。米三百石を出してあげよう。しかし、あとから話を変えたりはしないだろうな? それでは、満月の日に連れにこよう」
沈清の孝心に感動した船乗りたちは、こころよく三百石をさしだすことを約束しました。
沈清は喜びました。そして、
「父が気づかないように米三百石を夢恩寺に直接おくってください」
とたのみました。
「これで仏様との約束を守ることができた。お父さんは目が見えるようになるはずだ」
沈清の心は、飛ぶように軽くなりました。たとえ自分は死んでも、父の願いをかなえられるようになったことが何よりもうれしかったのです。
沈清は家に帰って、すぐに父に言いました。
「お父さん、きょうじゅうに供米三百石を夢恩寺にささげることができるようになりました」
「なんだって? おまえはわしをからかおうとしているのか」
「わたしがお父さんをからかうですって」
「そうだ、幼いおまえがどうやって三百石もの米を手に入れたというのだ」
「実は、数日前、大臣のお宅に行ったとき、その家の婦人がわたしを養女にしたいとおっしゃったのです」
「その方が、よりによってなぜおまえを養女にするというのだ?」
「一人で寂しく暮らしていらっしゃる大臣のお宅の奥様が、私を気に入ってくださったようなのです」
「それで?」
「その方がお父さんの気の毒な事情を知って、米三百石をこころよく出してくださることになったのです」
「ほう、それはそれは、本当にありがたいお方だ!」
沈盲人は、娘の言うことを信じて、手放しで喜びました。
「これで、お父さんは目が見えるようになったのです。うれしいでしょう?」
「もちろん、うれしいとも。ところで、これからは大臣のお宅に入って暮らさなければならないのか?」
「はい、今度の満月の日に行くことにしました。でも、一人で暮らすお父さんが心配です」
「わたしの心配はするな。おまえは大臣のお宅で何不自由なく暮らせるし、わたしは目が見えるようになって何でもできるのでよいではないか」
沈盲人は、目が開けるようになったという喜びでにこにこしました。このような父を見て、沈清はぽろぽろと涙を流しました。
「かわいそうなお父さん‥‥。いつか、わたしが竜王様にささげられたことを知ったとき、どんなに胸を痛めるだろうか。いずれにしても、仏様の恩恵によって目が見えるようになればいいのだが‥‥」
沈清の心は重く暗くなりました。
この日から、沈清は家を出る準備を始めました。
父が着る服をきれいに洗って、きちんとたたんでたんすの中に入れ、古い帽子もほこりを払って、手入れをしておきました。
また、庭に生えた雑草もすべて抜き取り、家の中をすみずみまできれいにみがきました。
出発の前日、沈清は、母のお墓に訪ねていって別れのあいさつをささげました。
「お母さん! 顔も知らないお母さんのお墓に訪ねてくるのも、きょうで最後です。どうぞかわいそうなお父さんを守ってください。お母さん‥‥」
沈清はむせび泣いたため、のどが詰まってそれ以上言葉をつなぐことができませんでした。
家に帰ってきた沈清は、父の隣にしゃがみこみ、父が眠りから覚めないように声を殺して一晩中泣きつづけました。
「コケコッコー!」
一番鶏が鳴きました。
沈清は、心を込めて最後の朝食の準備をしました。
「清よ、きょうのおかずは特においしいなあ!」
ご飯をおいしそうに食べた沈盲人は、ご飯の器をきれいに空にしてから
「きょうは大臣のお宅に入っていく日だろう? 昨晩、夢で、おまえがきれいな車に乗って、広い海に向かって走っていく夢を見たよ。きっと、おまえが貴い身となって良い所に行く夢だろう」
と言って、早く行く支度をするようにとせきたてました。
沈清は、ますます悲しみが込み上げてきました。そして、もうこれ以上耐えられなくなって、思わず泣き崩れてしまいました。
「ああ、かわいそうなお父さんを一人残してどうして行けるだろう‥‥」
「えっ、清よ、突然どうしたのだ? まったく会えない所に行くわけでもないのに」
沈清は、もうこれ以上父をあざむくことができませんでした。それで、供米三百石で売られるようになったことを打ち明けてしまいました。
沈清の話を聞いて、沈盲人は愕然としました。
「なんだって? 供米三百石でおまえを売っただって? それは本当か?」
沈盲人は、娘の話が信じられず、沈清の体をゆすって何度も確認しました。そして、それが本当だということが分かった沈盲人は、跳び上がって娘を大声でしかりました。
「この愚か者! 子供を殺して目が見えるようになって、それで幸福になるとでも思っているのか! この世で父親を悪者にすることが孝行だとでも言うのか! 目も見えるようになりたくないし、仏様にもすがりたくない! すぐに寺に行って米を取り返してこい! そして、その残忍な船乗りたちに返してやれ!」
沈盲人の怒鳴り声を聞いて、隣家の人々が集まってきました。
「まったく、清の孝心はけなげなのだが、沈盲人はどんなに心が痛いだろうか」
「痛いのは、清の心のほうがもっと痛いだろう」
隣家の人々は、この哀れな事情にため息をついて涙ぐみました。
沈盲人は、娘のそでをつかんで、行かないでくれと哀願しはじめました。
しかし、沈清は、
「仏様との約束を破れば、その罰で、おとうさんが足のなえた人か大蛇になるというではないですか。船乗りたちとの約束を破ることも道理ではありません。ですから、どうかわたしをつかまないでください」
と言って、そでをふりはらいました。
目の見えない沈盲人がどんなにあがいたところで、沈清をつかまえておくことなどできませんでした。
沈清は、泣いている父の前にひざまずき、深々と別れのあいさつをささげました。
沈清は、表で待っていた船乗りたちのあとに従って家を出ました。
「清よ! このかわいそうな子よ! わたしを置いていかないでくれ。おまえが行くのなら、わしも行く。いや、おまえが残って、わしが行こう!」
沈盲人は、はって土間まで出てきて、ありったけの声でわめきました。その声に胸が引き裂かれそうになった沈清は、両手で耳をふさぎました。
「清よ、行かないでくれ、清よ! アイゴー!」
声をあげて泣いている父を置いて去っていく沈清の足取りは、ふらふらと酒に酔った人のようにふらつきました。
涙はぼろぼろこぼれおちて襟をぬらし、かみしめた歯で切れたくちびるからは血が流れました。
天も泣き、地も泣いているのか、突然、ぽつぽつと雨粒が落ちはじめました。
船は、青い海をすべるように進みました。
船べりに立って故郷の方角を心うつろに見つめていた沈清の心は、次第に悲しみから恐ろしさに変わっていきました。
沈清は悲しさに泣き、そして恐ろしさに泣きました。
まもなく雷のような音をたてて山のような波が恐ろしく渦巻いている場所が現れました。そこがまさしく印塘水という場所でした。
「準備しなさい」
船乗りの言葉に、沈清は新しい服に着替え、船べりにひざまずきました。
「お願いします、お願いします。天の神様にお願いします。わたしははかなく死んだとしても、どうかお父さんの目が開いて、世の中を見ることができるようにしてください」
沈清は、両手をすりあわせながら、祈って、また祈りました。そして、船乗りたちにお願いしました。
「どうか無事に船旅を終えられ、お金をたくさん稼いできてください。そして、再び国に戻ったときは、わたしの父を訪ね、目は開いたのか、またどのような暮らしをしているのか調べてみてください」
「それは心配することはない。せめてあの世だけでも良い所に行きなさい」
船乗りたちは、まもなく太鼓をどんどん鳴らしはじめました。
沈清は、へさきに立ちました。最後に、もう一度、故郷の方角を見つめました。そして、両手を胸に当てて握り、じっと目を閉じました。
沈清の体が船べりにふわっと浮き上がったかと思うと、次の瞬間、黒い波の間に花びらのように舞い落ちていきました。
つづく