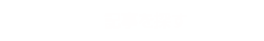【韓国昔話17】悲しいキキョウの花
昔、ある村にキキョウという娘が住んでいました。
キキョウは、美しく、心のやさしい娘でした。村の人々は、キキョウに会うと、いつもキキョウをほめました。
しかし、キキョウの顔には、いつも陰りがありました。なぜなら、キキョウは、父母も、兄弟も、親戚もいない孤児だったからです。
ある日、泉で水をくんでいると、一人の少年が近づいてきて、キキョウに声をかけました。
「水を飲みたいので、器を少しかしてくれませんか」
キキョウは、だまって器に水をくんで少年に与えました。
その日から、その時間になると、決まってキキョウは泉に水をくみに行き、決まって少年は、泉に水を飲みに来るようになりました。
少年は、家柄の高い両班の息子で、人々から「パウ坊ちゃん」と呼ばれていました。パウは、いつもキキョウにあたたかく接しました。
キキョウは、パウを「お兄さん」と呼ぶようになりました。キキョウとパウは、日増しにどんどん親しくなっていきました。
ある日、パウは、キキョウの両肩をつかんで言いました。
「いつか、ぼくのお嫁さんになってほしい」
その日以来、キキョウは、パウのこの言葉をいっときも忘れませんでした。パウが近くにいないときでも、キキョウは、パウを思うと心があたたかくなるのを感じました。
やがて、キキョウの顔は、みちがえるように明るくなりました。
そのようなある日のこと、パウの思いもよらぬ言葉に、キキョウの幸福はこなごなにくだかれてしまいます。
パウは、キキョウに言いました。
「勉強をするために海を渡って中国に行きます。一度行けば、十年はかかるでしょう」
パウは中国へ旅立っていってしまいました。
パウが去ったのち、キキョウの顔には、再び昔のように陰りがさすようになりました。
キキョウは、どうやって十年を待とうかと考えたすえ、山の奥深くにあるお寺をたずねていきました。
キキョウは、お寺の住職に言いました。
「ここに住まわせてください。そのかわりに、わたしが掃除もし、洗濯もし、ご飯も炊いて、山菜もつんできます」
キキョウは、お坊さんから勉強も学び、仕事も手伝いながらパウを待ちました。
そのようにして、一年、二年と歳月は流れ、いつしか、パウが約束した十年の歳月がたちました。
キキョウは、くる日もくる日も、海を見下ろしながらパウを待ちつづけました。しかし、春が過ぎ、夏になっても、パウは帰ってきませんでした。
見るに見かねた住職は、村に下りていって女衆にたずねてみました。すると、女衆が答えました。
「パウ坊ちゃんは、勉強がすべて終わって帰ってくる途中であらしに遭い、海に落ちて、ゆくえが分からないそうです」
住職はとても驚きました。
寺に帰ってきた住職は、ためらったのち、意を決して、女衆から聞いた話をキキョウに伝えて、こう言いました。
「もう、パウを待ちつづけるのはやめなさい」
キキョウは、涙を流しながらも、その話を信じようとしませんでした。しかし、一年が過ぎ、二年が過ぎても、パウは帰ってきませんでした。
「やはり、もうお兄さんは帰ってこないのか」
キキョウは、お寺を出て、さらに深い山奥に入っていき、一人で生活を始めました。世の中との縁を切って、パウのことを忘れようとしたのです。
ところが、どんなに忘れようと努力しても、忘れることはできませんでした。キキョウはパウを思い出すたびに山の神に祈るようになりました。
「山の神様。もう私は、お兄さんのことを思い出しません。もしわたしがお兄さんを思い出せば、わたしに罰をお与えください」
時は過ぎ、キキョウの顔にはしわができ、頭には白髪が目立つようになりました。キキョウは、やはりパウを忘れることができませんでした。
「ああ、どうして、今でもお兄さんのことを思い出してしまうのだろう」
我慢できず、キキョウは、また裏山に登って、時がたつのも忘れて海を見つめました。
すると、山の神が現れてキキョウに言いました。
「キキョウよ。どうしておまえはパウを忘れられないのだ? パウのことを思い出せば、罰を与えてくれとまで祈ったではないか」
「はい、山の神様。忘れようと努力しましたが、どうしてもお兄さんを忘れることができません。どうか一目でも、お兄さんに会わせてください」
「だめだ。おまえは今から、死ぬことも、老いることもせずに、パウだけを待ちつづけなさい」
山の神がそう言うと、その場で、キキョウは花になってしまいました。
それが、今日わたしたちが目にするキキョウの花であり、その花の色は、痛めた心の傷があざになって紫色をしているのだそうです。
終