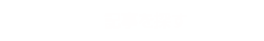【韓国昔話40】沈清伝1「娘をもうけて、妻を失う」
盲人は、お手洗いから出てくると、地面から突き出た石につまずいて転んでしまいました。
盲人は、ゆっくり起き上がってつぶやきました。
「はっはっ、夜空に星がきらきら輝いていたので、しばらく見とれていたらこのざまだ」
ちょうどその前を通りがかった村人が、その言葉を聞いてクックッと笑いました。
なぜかというと、星がきらきら輝く夜空どころか、雲がいっぱいに広がった真昼だったからです。
真昼に星がきらきら輝いているととぼけたこの盲人の名前は、「沈学奎(シムハッキュ)」です。
沈学奎は、目が不自由な境遇にもかかわらず、盲人でないようなふりをして、よく人々を笑わせました。
沈学奎は、今から千年くらい前に、黄海道黃州郡挑花洞に住んでいた人です。
もとは立派な家門に生まれた、すっきりした顔立ちの行いの正しい若者で、二十歳のときに、郭氏の姓を持つしとやかな娘を妻に迎え、幸せに暮らしていました。
ところが、突然、家計が傾いて暮らし向きが苦しくなると、泣きっ面に蜂で、父母兄弟が一人ふたりと、悪い病気であの世へと去っていってしまいました。
沈学奎も病気にかかり、あやうく死にそうになりましたが、その後、かろうじて助かりました。
しかし、健康だった沈学奎の目は、完全に見えなくなってしまったのです。目が見えなくなった沈学奎を、人々は「沈盲人」と呼びました。
沈盲人は、気立ての優しい妻の真心のこもった世話を受けながら、どうにかこうにか暮らしていました。
沈盲人の妻は、朝早くに日雇いの仕事に出掛けていっては、夜遅くに帰ってきました。
沈盲人は、だれもいない家に一人座って、あっちに転がったり、こっちに転がったりしながら退屈な時間を過ごしました。
そして、「もう妻が帰ってくる時間になった」と言っては、耳をそばだて、土間から庭に、庭から土間に出たり入ったりしました。
そうしているうちに、しおり戸の前を通りがかった隣の家の夫人の足音を妻の足音とかんちがいして、
「おまえ、今、帰ったのか」
と、かけよって手を握ろうとすると
「まあ! 何をするのですか!」
と、すごい剣幕で手をふりはらわれてしりもちをつくことが一度や二度ではありませんでした。
また、仕事場から帰ってきた男衆の足音を聞き、
「きょうは、どこかよい所にお出かけのようですね。いってらっしゃい」
と早合点して言ったりして、あとから腹をかかえて笑われることもありました。
いずれにせよ、沈盲人の夫婦は、人々がうらやむほど仲むつまじく暮らしていました。
ところが、いつしか沈盲人には、人知れず暗い顔をしてため息をつく癖がつくようになりました。
「家系を継ぐ子供がいなければならないのだが‥‥」
沈盲人の憂いは、まだ子供を持つことができないことから生まれたものでした。
四十歳を超えたある日のこと、沈盲人は、とうとう耐え切れなくなって妻に言いました。
「わたしは、目の見えない盲人なのに、あなたのような善良な人と出会って、身のまわりの世話をすべて受けながら楽に暮らしている。だから、あなたに何の不満があろうか。しかし、たった一つ残念なことは、家系を継ぐ子供がいないことだ」
「わたしも、そのことを常に恥ずかしく、申し訳なく思っています。しかし、子供は天が授けてくださるものなので、ただただ切ないばかりです」
「精誠を尽くせば天も感動するというではないですか。今からでも、名の通った山と寺を訪ね、山の神様と仏様に子供を持てるように精誠を尽くしてみましょう」
沈盲人の妻は、一人で家計を切り盛りするだけでも手に余る状況でしたが、夫の切なる願いを無視することはできませんでした。
沈盲人の妻は、日雇いの仕事をしながら、合い間合い間に名の通った山と寺を訪ねてまわりました。
「石仏の鼻をけずって飲めば、子供が生まれるそうだ」という言葉を、だれかから聞いた沈盲人の妻は、石仏を見れば、その鼻をかいて石の粉をけずりだして飲みました。
そのようにしていると、家から近い夢恩寺の入口の石仏たちは、すぐに鼻が平べったくなってしまいました。
このようにして精誠を尽くしてから三年目のことです。
その日は、四月八日のお釈迦様の誕生日でした。
澄んだ夜空を五色の雲が覆ったかと思うと、一人の仙女が鶴に乗っておりてきたのです。
仙女は、沈盲人の妻ににこやかにお辞儀をして、
「わたしは、北斗七星の六番目の星です。仏様の命を受けて訪ねてまいりましたので、どうぞ私をお受けください」
と言うと、妻のお腹の中に霧のように抱かれて入っていきました。
沈盲人の妻は、びっくりして目を覚ましました。それは夢だったのです。
夢の話を聞いた沈盲人はにこにこして言いました。
「これは胎夢(妊娠のきざしとなる夢)に違いない。あなたのこの上ない精誠に感動した仏様がわたしたちに子供を授けてくださったのだ」
沈盲人が言ったとおり、沈盲人の妻の夢は胎夢でした。夢を見てから四か月が過ぎると、妻のおなかがふっくらとふくれてきたのです。
赤ん坊を身ごもってから十か月目、沈盲人の妻は、ついに赤ん坊を生みました。
「どれ見てみよう、わたしの子供」
沈盲人は、生まれたばかりの赤ん坊のやわらかい体をあちこちなでてみてから言いました。
「あなたが苦労の末に得た赤ん坊は娘だったなあ。しかし、息子でなければいけないということはない。年を取ってからもうけた娘なので、十人の息子もうらやましくない」
沈盲人は、そう言いながらも、少し寂しそうな表情を浮かべたり、そうかと思ったら、再びからからと笑って喜んだりしました。
ところが、赤ん坊を生んだ沈盲人の妻は、そのまま病気にかかって床にふしてしまいました。
目が見えない上に貧しい沈盲人は、病にかかった妻のために薬一服もまともに飲ませてあげることができませんでした。
ある日、沈盲人の妻は、夫の手を握り、ぽろぽろと涙を流しながら言いました。
「あなた、わたしはやはり寿命が尽きたようです。目の前の見えないあなたと、生まれたばかりの赤ん坊を置いて先にいかなければならないので、胸が張り裂けそうです」
「あなた、なぜそのように気の弱いことを言うのだ? あなたがいなくて、どうやってわたし一人で幼い子供を育てていくのだ?」
「いいえ、わたしにはもう助かる見込みがありません。ですから、わたしの最後の願いを聞いてください」
「話してみなさい」
「もしこの子が無事に育てば、わたしのお墓に連れてきて、この母に会わせてください」
「うん、そうしよう。せめてお墓の前で、あなたに会わせてあげよう、うんうん」
「そして、赤ん坊の名前は『清』にしてください」
「清? 清とは?」
「清く澄んだ目ということです。あなたの澄んだ眼となってくれることを願う心から、『清』と名づけたいのです」
「うん、うん、そうしよう」
沈盲人が肩をふるわせて泣いているあいだに、妻の息は次第に細くなっていきました。
そして、白い唇をふるわせながら、
「清、清よ‥‥」と低く呼びながら、沈盲人の妻は息を引き取ってしまいました。
沈盲人は、しばらくすすり泣いていたため、妻が亡くなったことも気づきませんでした。
かなりたってから、何の気配もないので、妻の鼻の前に手を当ててみた沈盲人は、
「ああ、わたしの妻よ! どうして息をしていないのだ?」
と言って声をあげて泣きました。
づづく