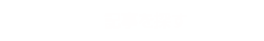【韓国昔話12】石仏の血の涙
とても人情味に欠けた、思いやりのない人々ばかりが住んでいる村がありました。村の人々は、旅人がたずねてきても、物置小屋さえ貸してあげませんでした。
ある蒸し暑い夏の日、一人のお坊さんが、その村をたずねてきました。村の人々は、お坊さんを見て、すぐに門を閉じて鍵をかけてしまいました。
村を一回りしたお坊さんは、ある家の前に立ちました。その家は、ほかの家とは違って、半分ほど門が開いている家でした。
「この家のご主人はいらっしゃいますか」
お坊さんが家の中に向かって声をかけました。すると、
「どちらさまですか」
と言って、家の中から、気のよさそうなおばあさんが出てきました。
「とおりすがりの旅人です。残った冷や飯でもあれば、ひとさじいただけないでしょうか」
「ああ、そうですか。どうぞ、中にお入りください」
おばあさんは、ほかの村人とは違って、とても親切でした。お坊さんは、おばあさんがつくってくれたご飯をおいしく食べました。
ご飯を食べ終わったのち、お坊さんは、家の外を見回して言いました。
「この村の裏山に石仏があるでしょう?」
「はい、あります」
「その石仏が血の涙を流す日、この村には大きな災いがふりかかるでしょう。もし石仏が血の涙を流せば、すぐに高い所に避難してください」
話し終えると、お坊さんは、おばあさんにお礼を言って、そのままどこかに行ってしまいました。
村に大きな災いがふりかかるという言葉に、おばあさんは、とても恐ろしくなりました。
次の日から、おばあさんは、毎日、裏山に登って、石仏が血の涙を流していないかどうかを調べました。
ある日、村の人々がおばあさんにたずねました。
「ばあさん、なぜ、毎日、裏山に登るのかね?」
「裏山の石仏を調べてくるためだよ。あるお坊さんがおっしゃったのだが、裏山の石仏が血の涙を流す日、わしらの村に大きな災いがふりかかるそうだ」
おばあさんは、心配そうな顔をして言いました。
すると、その話を聞いた村の人々は、腹を抱えて笑いだしました。
「石仏が血の涙を流すだって? そんなばかげた話がどこにある?」
「そいつは、もしかしたら、頭のおかしな坊主だろう」
村の人々は、おばあさんの話を信じませんでした。
「お坊さんのお話を、そのように笑い飛ばしてはいけないよ」
おばあさんは、人々が自分の話を信じてくれないので、もどかしく思いました。
おばあさんの言葉に、村の青年たちは、いたずらっ気がわいてきました。
「おれたちで、石仏の目に血をぬらないか?」
「何の血をぬるのさ?」
「何の血でもいいではないか」
「よし、あした、すぐにやってみよう」
翌朝、青年たちは、おばあさんが登る前に裏山に登っていきました。青年たちは、石仏の目に犬の血をぬったのち、茂みの中に隠れて、おばあさんが登ってくるのを待ちました。
しばらくして、おばあさんが登ってきました。
いつものように、おばあさんは、石仏の目を調べるために、石仏に近づいていきました。石仏の目を見たおばあさんは、びっくりしてうろたえました。
「なんと、石仏が血の涙を流している!」
そう言うと、おばあさんは、突然、村に向かってかけおりはじめました。
おばあさんのようすを見ていた青年たちは、腹を抱えて笑いました。
「本当に、石仏が血の涙を流したと思っているようだ!」
「あのばあさんは、完全に頭がおかしくなっている!」
青年たちは、おもしろがって、おばあさんのあとを追って山を下りていきました。
山から下りてきたおばあさんは、すべての家々を回りながら叫びました。
「裏山の石仏が血の涙を流しましたよ! 早く高い所に登らなければなりませんよ!」
おばあさんが呼びかける叫び声を聞いた村の人々も、びっくりして家から飛び出してきました。
ところが、そのあとから来た青年たちが笑いながら言いました。
「石仏が血の涙を流すなんて、そんなばかなことがどこにある? われわれがいたずらをしただけだよ」
青年たちの言葉を聞いて、村の人々も、安心してからからと笑い飛ばしました。そして、
「あのばあさんは頭がおかしくなったようだ」
と言ったりもしました。
おばあさんは、しかたなく、一人で山に登っていきました。そうして、おばあさんが山に登り終わったときです。
突然、真っ黒な雲が空をおおったかと思うと、雷と共に大雨がふりだしました。村は、すぐに洪水になりました。
村の人々と家々は洪水にのみこまれ、跡形もなくなってしまったそうです。
終