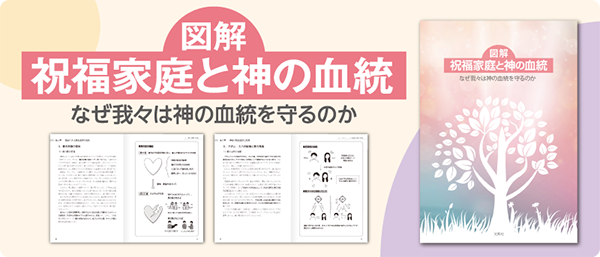共産主義の新しいカタチ 46
霊的存在としての人間に科学的に迫ろうとしたウォレス
2025.01.15 17:00

共産主義の新しいカタチ 46
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
「心霊」への科学的アプローチ
ウォレスと「精神世界」①
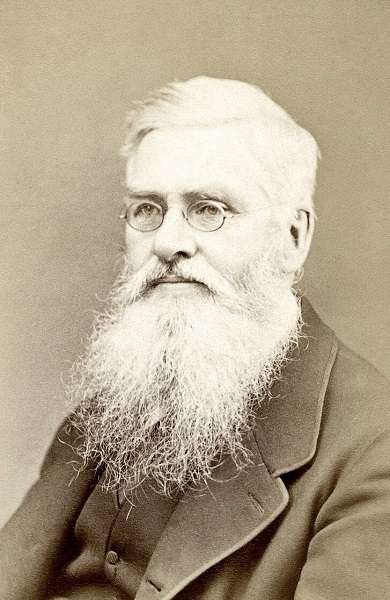
「進化論」を発表したチャールズ・ダーウィンはしだいに(『人間の由来』以降)、人間の脳や精神、道徳性も「動物から(目的もなく自然選択によって)進化したもの」と考えることで、生物学的にはエルンスト・ヘッケルらの発生学と結びつき、「生命ではない元素から有機化合物、さらには生命体への《進化》」、「サル(類人猿)から人間(ヒト=ホモ・サピエンス)への《進化》」が一般的に進化論と受け止められます。
そして、ヒトの間にも「類人猿に近い人種から最高度に発達した白人種」だとの考え方が19世紀から20世紀の欧米世界では「普通の人間観」でした。
それがある意味で人種差別的な価値観を正当化してきたとも言えますが、その極致とも言えるのがまさに「優生思想」「優生学」で、これを英国を中心に担ったのが、ほかならぬゴルトンやレナード・ダーウィンなどの「ダーウィン一族」だったことを紹介しました。ダーウィン家は学者や医師、投資家などまさにブルジョア上流階級でした。
測量士から教師、昆虫学の研究者へ
一方、後にダーウィンと進化論の論文の「共同提出者」となるアルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823~1913)の生涯は、実に興味深いものがあり、今回はウォレスが「霊的存在としての人間」を科学的に迫ろうとしたことについて論じてみましょう。
ダーウィンが華麗なるインテリ階級出身なのに比べ、ウォレスは中流階級出身ですが生活は貧しく、実業学校に進み見習い測量士となり専門的な生物学の教育は受けませんでした。測量士や教師の職業に就きながら、やがて天才的昆虫学者のヘンリー・ベイツと出合い、1848年から1852年にかけ昆虫の標本採集のために南米を共同で旅行。
その後自ら研究者となり、1854年から1863年にかけてマレー諸島を探検。この間、動物相の世界的地理分布である東洋区とオーストラリア区の境界線を発見し、これは今でも「ウォレス線」と呼ばれています。
ウォレスはまた、ダーウィンのようにマルサス『人口論』を読み自然選択を思い付きます。つまり生物は全て生まれる数に比べ、成体となる数はわずかで、熾烈(しれつ)な生存闘争の果てに適応的に少しでも有利な形質を持った個体が、優先的に生き残る可能性が高く、それが「生物種の変化」をもたらすという考えです。
しかし、ウォレスは自分と同じ考えを持つダーウィンの存在を伝え聞き、謙虚にもダーウィンに「お伺い」を立て、自分の論文を発表する了解を得ようとします。ダーウィンは、すでに1830年代には自然選択説を思い付いていましたが、20年以上も自説を公表せず、さまざまな反論を予測し、自説を裏付ける証拠を集めていたためのようです。
自然選択説をめぐるダーウィンとの確執
しかし、第43回でも述べたように、ダーウィンは友人の地震学者ライエルに仲裁を依頼し、二人の論文は1858年のリンネ学会で同時に発表されたのです。そして翌1859年に『種の起源』が刊行されました。
ウォレスは、測量士出身で職人気質から、厳密にデータのみを分析し、科学理論に思想性を持ち込むことを嫌うという態度が、逆にやがて「科学の限界性」を実感することになったと言えるかもしれません。
二人の立場の違いは、「人間の進化」をめぐり決定的となります。ウォレスは、「人間の知性の由来は自然選択では説明できない」と主張。彼は旅行先で出会った未開人の脳の潜在能力が、文明人と全く差がないことに気付いた。実際に彼らを英国に連れて行くと、すぐに英語を覚え文明生活にも馴染み、数学や哲学さえも理解することができました。つまり未開人は、「知的に劣っているのではなく、その能力を使っていないだけ」だったのです。
(続く)
★「思想新聞」2024年12月15日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「進む日本文化の破壊」2025年1月9日 竹ノ塚駅