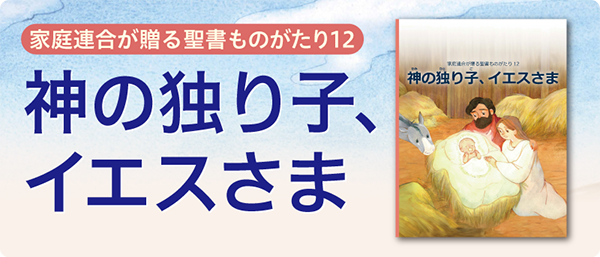3分で社会を読み解く 49
「解散命令」はなぜ国際法に違反するのか?
2025.01.06 22:00

facts_3分で社会を読み解く 49
「解散命令」はなぜ国際法に違反するのか?
ナビゲーター:魚谷 俊輔
パトリシア・デュバル弁護士が2024年9月に「日本:統一教会を根絶するための魔女狩り」と題する報告書を複数の国連特別報告者に提出したことは、すでに第35回で紹介した。
同報告書は、日本政府が宗教法人法第81条1項に基づき、家庭連合が「公共の福祉」を著しく害したと認められるために宗教法人の解散命令を請求したことを、国際法違反であるとしている。
それでは国際法と日本の法律の間にはどのような齟齬(そご)があるのだろうか。
パトリシア・デュバル弁護士は「法的分析」と題する新たな報告書を作成し、その中でこの点をより具体的に説明している。
国際人権基準においては、信教の自由は最も基本的な人権の一つであるため、国家がそれを制限するには明確な根拠が必要である。
それは日本も批准している「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」の第18条第3項に規定されている。
これは網羅的リストと呼ばれ、以下の目的に必要な制限のみを課することが可能であり、例外は許されていない。
一つ目は、公共の安全や秩序に対する脅威を防ぐためで、これは具体的にはテロ行為や国家転覆の企ての阻止を指す。
二つ目は、健康が危険にさらされる場合で、これは例えば宗教儀式における薬物使用などの規制を指す。
三つ目は、道徳の保護であり、これは例えばポルノに関する制限などを指す。
四つ目は、「他者の基本的な権利」を守るためだが、これは自由権規約で規定している基本的な権利、すなわち身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などを保護する場合に限定される。
要するに、国家が国民の信教の自由を制限することは、これほど明確で差し迫った理由がなければ許されないというのが国際人権基準なのである。
それに比べると日本政府が解散命令の根拠としている「公共の福祉」という概念は曖昧かつ無限定であり、あまりにも広範囲に適用可能であり、全体主義国家のように、恣意(しい)的かつ独断的な方法で適用され得る概念であるため、国際人権基準と直接対立するとデュバル弁護士は指摘している。
だからこそ国連の自由権規約人権委員会は日本に対し、宗教的信念を表明する権利を制限するために「公共の福祉」という概念を用いるのをやめるよう繰り返し勧告してきたのである。
しかし「公共の福祉」という言葉は、憲法12条、13条、22条、29条で用いられており、宗教法人法でも法人解散の根拠として規定されている概念だ。
今後、日本の司法が国際人権基準と国内法の齟齬にどのように折り合いをつけるかが注目される。
【関連情報】
Bitter Winter 日本語記事:
日本における統一教会訴訟:法的分析3
「公共の福祉」と「社会規範」