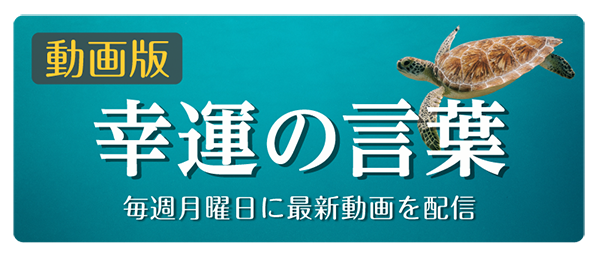3分で社会を読み解く 50
「宗教2世」について考える(前)
2025.01.13 22:00

facts_3分で社会を読み解く 50
「宗教2世」について考える(前)
ナビゲーター:魚谷 俊輔
「宗教2世」というネーミングはNHKが2021年ごろから広めたものであるが、安倍元首相銃撃事件以降に家庭連合に対するバッシングが激しくなる中で、マスコミ全体が使うようになった。
事件後、「小川さゆり(仮名)」さんが「宗教2世」のアイコン的存在となり、『小川さゆり、宗教2世』(小学館、2023年)という自伝的著作が出版されるまでになった。
「宗教2世」についてWikipediaが、「家族(両親など)が宗教を信仰している家庭で生まれ育ち、家族(両親など)の意思で幼い頃から宗教に入信させられている人達のことを指す」と説明しているように、この言葉は不本意ながら信仰を強制されている人々というニュアンスで使われている。
さらに家庭連合の「宗教2世」は、多額の献金と貧困、ネグレクト、生きづらさ、などのネガティブなイメージで語られることが多い。
櫻井義秀氏の著作『統一教会:日本宣教の戦略と韓日祝福』(北海道大学出版会、2010年)の中でも、「残念ながら子ども達はまさしく不本意な人生に変えられたのだ」と記述されている。「親ガチャ」という侮蔑的な表現にも彼の本音が表れている。
私自身は、「宗教2世」という言葉は多くの問題があり、使うべきではないと考えている。
なぜなら、特定宗教の信仰を持った家に生まれること自体が問題であるかのように捉えられ、出自による差別や偏見を助長する恐れがあるからだ。
それでなくても、人類の歴史は宗教的出自による差別の例に満ちている。
ユダヤ人の家庭に生まれたというだけで迫害の対象になったのは、それほど遠い昔の話ではない。
ここで「2世」という表現が意味するものについて深掘りしてみたい。
つまり、なぜ宗教「2世」問題といわれるのに、「3世」「4世」問題とはいわれないのかということだ。
Wikipediaによる「宗教2世」の定義には、伝統宗教を先祖代々信じている人々も含まれるはずだ。
キリスト教で幼児洗礼を受けた人などは、この定義によればまさに「宗教2世」であろう。
ここで、親から子供に信仰を継承すること自体は全くノーマルであることを大前提として押さえておきたい。
伝統的社会における親から子への信仰相続は「社会化」と同じプロセスであった。
仏教の檀家(だんか)は「家の宗教」であり、神社の氏子も先祖から受け継ぐものである。イスラムでは子供が親の信仰を相続するのは義務であり、他宗教への改宗は死刑に値する。
こうした社会では、「宗教2世」どころか「宗教3世」も「宗教4世」も当たり前の話であり、問題視されることはない。
にもかかわらず、あえて「宗教2世」だけを問題視するところに差別の本質がある。