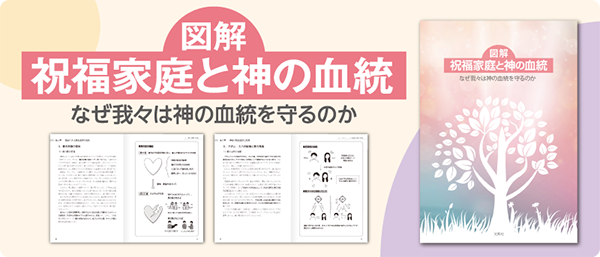3分で社会を読み解く 51
「宗教2世」について考える(後)
2025.01.20 22:00

facts_3分で社会を読み解く 51
「宗教2世」について考える(後)
ナビゲーター:魚谷 俊輔
「宗教2世」という言葉が、安倍元首相銃撃事件以降に家庭連合に対するバッシングが激しくなる中で、人権問題としてマスコミに喧伝(けんでん)されるようになった。
そもそも、親から子供に信仰を継承すること自体は全くノーマルであるが、信教の自由が保障された現代社会においては、子供にも宗教の選択権がある。それ故に親の信仰を継承するかどうかを巡って親子の葛藤が生じる可能性がある。
この点に関しては伝統宗教も家庭連合も同じであり、家庭連合の信仰継承にだけ何か特別な問題があるわけではない。それをことさらに「宗教2世」という言葉を用いて、人権問題として取り上げようとするところに、マスコミの偏見が見て取れる。
ここで、あえて宗教「2世」であって、「3世」でも「4世」でもないのは、この言葉を用いる側が批判する宗教の親世代が、信仰の第一世代であることを含意しており、要するに新しい宗教(カルト)を標的とした言葉であることを表している。
すなわち、親と子の二世代しか存在しないくらいの新しい宗教をターゲットにしているということだ。
新宗教運動は、既存の伝統宗教に満足することのできない教祖によって、同じような不満を抱えた信徒たちが感化されて創唱されることが多い。
当然のことながら、生まれたばかりであれば教団の規模は小さく、既存の伝統宗教や社会一般に対して、批判的で対抗的な世界観を持っていることが多い。そうでなければ、新しい宗教を創唱する必要がないからである。
現代社会のマイノリティー宗教における信仰相続は、子供に対して価値観が大きく異なる「二つの世界」に生きるという状況を強いることになる。
すなわち、教団の中では一般社会に対して批判的で対抗的な宗教的価値観を教えられるが、同時に一般社会の学校に通い、就職すれば、世俗的な価値観と折り合いをつけなければならない。
マイノリティー宗教の二世が経験する葛藤の本質はまさにこのようなものだが、メディアの扱いは、「教団=悪、子供=被害者」という構図になりがちであり、二世が教団を離れることこそが問題の解決であると言わんばかりの報道が多い。
「宗教2世」の問題としてしばしば取り上げられる貧困、虐待、ネグレクトなどの問題は、個別の家庭問題として扱われるべきであり、同じ教団の信者でも状況は家庭ごとに異なる。
特定宗教の信者の家庭だからこうした問題があると決めつけるのは偏見である。もしこうした問題が本当に存在するとすれば、信仰の有無にかかわらず、支援の手が差し伸べられるべきである。
被害者としての「宗教2世」像は、マスコミがつくり上げたステレオタイプに過ぎない。