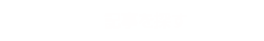【韓国昔話2】オソンとハヌムの機知で取り戻した金の仏像
オソンとハヌムが結婚したのち、科挙試験の準備のために、ある寺に入って勉強していたときの話です。
ある朝、お寺の講堂を管理しているお坊さんが、オソンとハヌムが寝起きする部屋に訪ねてきました。
「おふたかた、大変なことが起きたのですが、私を少し助けてください」
「大変なこととは、どういうことですか」
「講堂に安置されていた小さな金の仏像がなくなったのです。ご住職様がお知りになれば、とてもお怒りになります。どうにか探す方法はないでしょうか」
お坊さんは、とても不安そうに、今にも泣き出しそうな表情を浮かべて言いました。
「なんとまあ‥‥。誰が貴い仏像をもっていったのだろうか? 何か心当たりはありませんか」
「昨晩、寝ている間に誰かがもっていったようです。講堂の中も、お寺の中も、くまなく探したのですが見つからないのです」
「分かりました。一度、調べてみましょう」
「私も、もう一度探してみますので、どうかよろしくお願いします」
お坊さんが帰ったのち、二人は、部屋から出て、お寺の周辺を散策してみました。
昨晩、雪が降ったので、一面銀世界でした。
「お寺の周辺に足跡や人の通った痕跡がないのを見ると、間違いなくお寺の中にいる誰かが金の仏像をもっていったはずだ」
ハヌムは、そう言うと、くちびるをぎゅっと閉じました。
「そうだとすれば、お坊さんが仏像を盗むはずはなく、仏様を供養するために来た人の中の誰かがもっていったようだな」
とオソンが推測しました。
「うん、そのとおりだと思うが、むやみに人を疑うことはできないだろう」
「そのとおりだ。その上、仏様をまつっているお寺の中で荷物を調べることもできないし‥‥」
二人が考え込んでいると、昨日仏様の供養をするために来た若い夫婦が、
「お祈りが終わったので山を下ります」
と言って、お坊さんたちとあいさつを交わしていました。
それを見るなり、オソンとハヌムは目を合わせました。
「君の考えもそうか」
「うん、君もそのように考えたのだな」
二人とも、その若い夫婦が怪しいと思いました。
急な用事でもないのに、雪が溶ける前に山から下りようとすることが怪しかったのです。
オソンとハヌムは、部屋に戻って簡単に荷造りをしたのち、先ほど訪ねてきたお坊さんの所に行きました。
「お坊さん、しばらく山を下りてきます。うまくいけば、金の仏像をもってこられるかもしれません」
オソンの言葉に、お坊さんの顔に一瞬、笑顔が浮かびました。
二人は、急いで山の近道を下りていき、夫婦が通りそうな所で待っていました。
夫婦の姿が見えると、オソンとハヌムは分かれました。
待っていたオソンが夫婦に声をかけました。
「どこまで行かれるのですか」
「私たちは、京畿道の驪州のほうに行きます」
「あー、それはよかった。私もそちらの方面なので一緒に行きましょう」
オソンは、夫婦と連れ立って歩きはじめました。
しばらく行くと、今度はハヌムが現れ、一行は四人になりました。
もちろん、オソンとハヌムは互いに知らないふりをしました。
いつしかお昼時になりました。
四人は一緒にご飯を食べることにして、宿に入っていきました。
そして、一緒の部屋で食事を終えたのち、ハヌムは「先に出発します」と言って、荷物を担いで出てきました。
ハヌムが宿の門を出ようとすると、若い夫婦が走ってきてハヌムをつかみました。
「いや、何をするのですか」
「荷物が入れ替わりました。今、あなたが背負っている荷物は私のものです!」
若い男性は、目をまんまるくしてハヌムの担いでいる荷物を奪おうとしました。
「あれ、何をするのですが、間違いなく、これは私の荷物ですよ!」
ハヌムも、気勢をくじかれないように大きな声で言い返しました。
「こんなたちの悪いどろぼうがいるか! 人の荷物を自分の物だと言い張っている!」
「どろぼうだって? 私の荷物を私が背負っていくのに、何の言いがかりですか」
若い男性とハヌムがああだこうだと言い争っていると、人々が集まってきました。
そのとき、オソンが間に入って言いました。
「そのようにけんかをするのではなく、互いに荷物をほどいてみればいいではないですか」
「いいでしょう、そうしましょう」
ハヌムが荷物を下ろしながら言いました。
オソンは、ハヌムを見ながら尋ねました。
「まず、あなたの荷物からほどいてみましょう。荷物の中には何が入っていますか?」
「私の荷物の中には、金の仏像が入っています」
ハヌムがそう言うと、若い夫婦の顔は、みるみる青ざめていきました。
「それでは、荷物を開いてみなさい」
ハヌムが荷物を広げると、本当に金の仏像が出てきました。
すると、オソンが若い男性を見て言いました。
「この人の言葉どおり金の仏像が出てきたので、この荷物はこの人の物ではないですか。なぜ、あなたの物だと言い張ったのですか」
「いえ、私の錯覚だったようです。す、すみません」
オソンが詰め寄ると、若い男性はもごもごと口ごもりながら、自分の妻と席を外しました。
オソンとハヌムは、彼らを捕まえて郡の役所に引き渡そうかとも考えましたが、このような目に遭えば肝を冷やしたはずであり、まだ若い夫婦なので、一度は許してあげることもよいような気がして、そのままにしておきました。
オソンとハヌムは、冗談を言い合いながらお寺に帰ってきました。
「人の荷物をこっそりもって出てきたのだから、君こそどろぼうではないか」
「私がどろぼうなら、君は何だ? どろぼうと組んで事をはかったので、当然、君もどろぼうではないか。ははは」
「あー、そういうことになるのか。ははは」
終