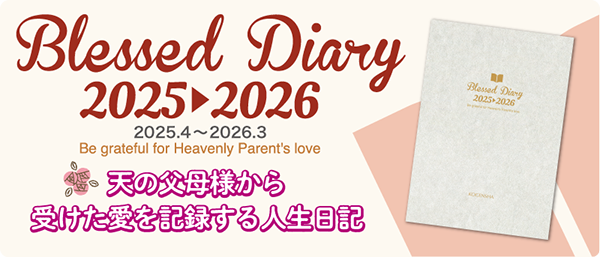ほぼ5分で読める勝共理論 71
戦後の学生運動
2025.03.06 12:00

ほぼ5分で読める勝共理論 71
日本共産党について⑩
戦後の学生運動
編集部編
「ブント」の登場
共産党の闘争路線は、1952年に選挙で惨敗することで完全に姿を消しました。
しかし共産主義を信奉する人たちは、この方針転換に強く反発していました。特に大学生の中には、「日本の革命は近い」と信じて献身的に活動していた人たちがたくさんいたのです。
それで方針転換に反発した人々は、新しい団体をつくりました。
これを共産主義者同盟、略して「ブント」といいます。ちなみにブントというのは、「同盟」という言葉をドイツ語に訳したものです。もちろん彼らは、「暴力革命」路線を訴えていました。
当時は、安倍晋三元総理のおじいさんである岸信介さんが総理大臣で、日米安保条約をより良いものにしようと取り組んでいた時でした。
社会では、「条約を改定すれば日本が戦争にまき込まれる」という批判が起きていました。この反対運動を「安保闘争」といいます。
2015年の安保法制(平和安全法制/2015年9月30日制定、2016年3月29日施行)でも全く同じ批判がありましたが、実は、これは当時の安保闘争をまねたものだったのです。
違っていたのは、反対運動に参加した大学生はほんのわずかしかいなくて、デモとか集会に参加していたのは、かつて学生運動をしていたお年寄りが大半だったということです。
話を元に戻しましょう。
当時の安保闘争で、もちろん共産党も厳しく反対していました。でも共産党としては、暴力的な活動では国民の支持が離れてしまう、選挙で負けてしまうと考えていました。だからデモを行ったり、国会に請願を提出したりするといった、非暴力的な活動をしていました。
ここに登場したのが先ほどのブントです。
彼らは国会に突入して、警備員を実力で突破して国会の議論を止めたりもしました。
彼らは「新左翼」と呼ばれて、「闘わない既成左翼、闘う新左翼」という言葉も生まれました。
そして彼らの活動に、たくさんの大学生が刺激を受けました。
自滅が共産主義の宿命
「こんな歴史の大転換期におまえは何もしないのか。そんな無責任が許されるのか」
そう言って、ほとんどの大学生が何らかの運動に参加しました。
特に安保条約の改定が国会で決議される時には、毎日のように数十万人のデモが国会を包囲しました。
デモ隊が機動隊と衝突して、東大生の樺(かんば)美智子さんが圧死するという事件も起きました。
学生らの運動は分裂と闘争を繰り返していました。
もともとマルクスの理論は、闘争によって発展するという理論ですから仕方ありません。そして互いに襲撃し合って、時には死人が出ました。こうした左翼団体同士の衝突を「内(うち)ゲバ」といいます。
やがて学生らの対立は過激化して、内ゲバの死者も100人を超えるようになりました。
日本も高度経済成長によって、だんだんと豊かになってきました。学生運動は国民の支持を失っていきました。
そんな中、連合赤軍という学生運動の中でも最も過激なグループが、「あさま山荘事件」という事件を起こしました。
彼らは自分たちの仲間12人をリンチで殺し、さらに人質を取って旅館に立てこもりました。警察官との銃撃戦は10日間にも及びました。
この事件はテレビで生中継されましたが、各テレビ局の視聴率の合計は最高で89.7%にもなりました。当日のNHKの報道特別番組は平均で50.8%を記録しました。
これは今でも報道特別番組の日本記録です。
この事件を通して、学生運動は急速に支持を失いました。
これが共産主義思想の行き着く先です。
革命に成功すれば中国やソ連、北朝鮮のように独裁体制になって、たくさんの人が犠牲になります。失敗すれば仲間うちで殺し合って自滅します。それが、共産主義の宿命なのです。
【関連書籍】
◆『よくわかる勝共理論~日本と世界の平和のために~』(光言社)