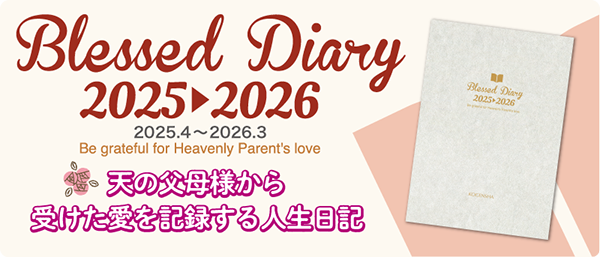3分で社会を読み解く 56
特定の信仰を持つ者を差別する野党案
2025.02.24 22:00

facts_3分で社会を読み解く 56
「不当寄附勧誘防止法」の問題点(5)
特定の信仰を持つ者を差別する野党案
ナビゲーター:魚谷 俊輔
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」は施行後2年が経過し、改正の時期を迎えている。この法律の問題点を指摘するシリーズ第5回である。
同法の成立過程では、寄付に対する「家族の取消権」について与野党の激しい対立が生じた。
野党側は「統一教会の問題の最大の焦点は、本人が献金をやめられない場合、またそれを変えることが本人には期待できない場合、家族が取り戻せるようにするにはどうしたらよいか、ということだ。われわれの案では、『特別補助制度』を作ることでこれを救済しようとしている」と主張した。
これは本人に献金をやめる意思がなく、また献金を取り戻そうとする意思がないときには、家庭裁判所が「特別補助人」に代理権を付与し、本人に代わって訴訟する権利を持つようにするという制度である。
例えば熱心に信仰している母親に対して、息子が「母はマインド・コントロールにかかっている」と主張して、裁判所から「特定補助人」に指定されれば、母親の意思に関係なく、息子は母親が献金したお金を取り戻すための訴訟を起こす権利を与えられることになる。
これは母親の財産権を侵害することとなり、憲法違反になる可能性がある。
かつては「準禁治産者」という制度があり、心神耗弱者や浪費者であるという認定をして、その宣告を受けた人が「保佐人」の了承を得ずに行った法律行為を取り消すことができた。しかしこれは基本的人権や自己決定権の侵害に当たる疑いがあることから、2000年に「成年後見制度」に置き換わった。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない人を保護するための制度であり、こうした精神上の障害が認められる人の場合には、補助する人(補助、保佐、後見、任意後見)の同意がないと財産上の処分ができないようになる。
この認定にも本人の同意は不要である。
要するに野党案の「特別補助制度」とは、特定の信仰を持つ者を精神障害者と同等であると見なそうとする制度であった。
これは従来の損害賠償請求訴訟では、どうしても本人が直接被害を訴えないと原告になれないので、それを助け出す知恵があればと思って考えたのだという。
結局野党案は実現せず、成立した法律では扶養されている子供などの養育費を取り戻すという範囲でのみ「取消権」を認めることとなった。
しかし全国霊感商法対策弁護士連絡会が2024年9月21日付で発表した「旧統一教会の被害救済のため法整備求める」という声明では、家族が信者本人に代わって献金を取り消し、その財産を管理することのできる制度(かつての準禁治産制度に類似の制度)を設けるよう求めている。
野党案を復活させるこのような改悪は、何としても防がなければならない。