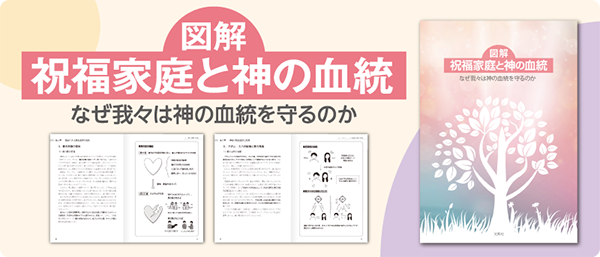3分で社会を読み解く 54
党利党略から生まれた妥協の産物
2025.02.10 22:00

facts_3分で社会を読み解く 54
「不当寄附勧誘防止法」の問題点(3)
党利党略から生まれた妥協の産物
ナビゲーター:魚谷 俊輔
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」は施行後2年が経過し、改正の時期を迎えている。この法律の問題点を指摘するシリーズ第3回。前回から、この法律の成立過程における問題を論じ始めた。
当初自民党は、「旧統一教会被害者救済新法」という通称で野党が提案していた法律に対して、信教の自由や財産権など、憲法で保障された権利に抵触するとの理由から後ろ向きであり、最初に動き出したのは野党であった。
2022年9月21日に立憲と維新が新法成立に向けて共闘することを公表。10月17日には立憲と維新が共同で「悪質献金被害救済法案」を衆議院に提出した。
立憲と維新の共闘が早い段階で成立したことに対して、自民党が警戒心を抱くようになり、自民党は立憲と維新の分断を図るようになる。
実務者レベルの与野党協議とは別に、茂木敏充幹事長(当時)が維新の幹部と頻繁に接触しながら、維新を取り込んでいった。そうして維新と立憲を分断させる中で、最終的には立憲にも譲歩させる形で政府与党案を成立させる方向に持っていった。
10月18日、岸田文雄首相(当時)は衆議院予算委員会で「救済新法」に関して、「今国会の法案提出を念頭に準備を進めていく」と発言した。
旧統一教会問題に対して後ろ向きだという野党の追及を甘く見ては、政権が持たないと判断したのであろう。
しかし野党案は実現不可能な無理筋の法案であることは分かっていたので、この時から首相官邸が一気に動き出した。法務省の専門家を消費者庁に集め、法律の専門家と消費者庁の見解を合致させる作業をして、内閣法制局をクリアできるようにしたのである。
この時点で岸田首相にとって、「救済新法」は何としても会期中に成立させなければならないマストの法案となった。閣法となれば可決される可能性は一気に高まる。
しかし、11月24日に政府案が提示されると、立憲の岡田克也幹事長(当時)は「40点じゃないか」とこれを批判した。
その後、「救済新法」を巡る国会審議は迷走し、与野党で喧々囂々(けんけんごうごう)の議論がなされたのち、妥協の産物として法案がまとめられた。
与党自民党が考えていたことは、旧統一教会に対して弱腰だと思われたくないので、法案成立に後ろ向きの姿勢を示すことはできないが、だからと言って無理筋な法律を通すことはできないということだ。
一方で野党は、実行不可能な無理筋の法律を提案することで、「自分たちは旧統一教会を厳しく取り締まろうとしているが、自民党はズブズブだから腰が引けている」と宣伝することで、正義の味方であるかのようなパフォーマンスを見せようとした。
こうした党利党略の産物として、現実から乖離(かいり)した、使い物にならない法律が出来上がってしまったのである。