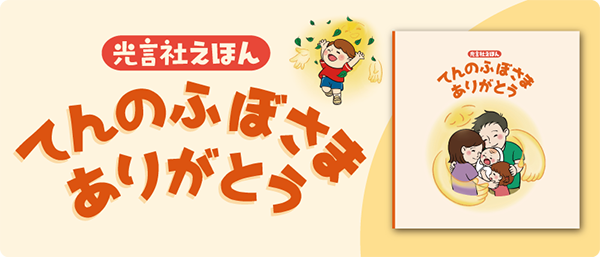3分で社会を読み解く 53
特定団体を狙い撃ちにした法律
2025.02.03 22:00

facts_3分で社会を読み解く 53
「不当寄附勧誘防止法」の問題点(2)
特定団体を狙い撃ちにした法律
ナビゲーター:魚谷 俊輔
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」は施行後2年が経過し、改正の時期を迎えている。この法律の問題点を指摘するシリーズ第2回。今回から、この法律の成立過程における問題を論じることにする。
同法は2022年7月8日に起きた安倍元首相暗殺事件をきっかけにして起こった家庭連合(旧統一教会)に対するバッシングを背景として、内閣が「旧統一教会被害者救済新法」という触れ込みで法案を提出したため、マスコミもその名称で報道し続けた。
この法律に関してはいくつかの誤解があるようなので指摘しておきたい。
まず「旧統一教会被害者救済新法」という通称から、過去において統一教会から被害を受けた人を救済するための法律だと勘違いしている人がいるようだが、そもそも新しく法律を作った後に過去の行為に対して遡及(そきゅう)的に違法性を問うことはできない。あくまで今後行われる行為に対してのみ新法は適用される。これを「法の不遡及」の原則という。
次に、この法律は宗教法人のみならずその他の法人を含む全ての団体(「等」が付いているので法人格を持っていなくても適用される)に対する寄付行為を規律するものである。
従って家庭連合のみに適用される法律ではなく、ひとたび施行されれば全ての宗教団体および法人に適用されるのであるが、宗教界から反対や懸念の声がほとんどなかったことを見ると、自分たちにもそれが適用されるようになることに対する自覚が薄いようだ。
そもそも特定の宗教団体を狙い撃ちにした法律など、信教の自由が保障された民主主義国家においては作れるはずがない。それができてしまったら、もはや法治国家とは言えない。
しかし問題は、この法律が制定される過程において国会でなされた議論は、その目的が旧統一教会に対する高額献金を規制することにあるとあからさまに語られ、その内容も実際に旧統一教会の活動に適用できるかどうかを巡って争われていたということである。
その意味では、立法趣旨においては「旧統一教会を狙い撃ちにした法律」といっても過言ではない。
ところが、この法律の文言には「統一教会」も「家庭連合」も一切出てこない。それどころか、「宗教」「宗教活動」「宗教団体」「宗教法人」などの表記もなく、全ての法人や法人でない団体までもが対象とされている。
これは真の立法趣旨を隠して、普遍的な法令であるかのように装いつつ、実際には家庭連合を狙い撃ちにしているという点で、法治国家にあるまじきゆがんだ立法プロセスであったことを物語っている。