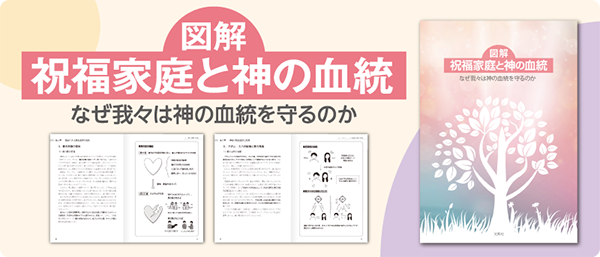ほぼ5分で読める勝共理論 61
上皇陛下はなぜ生きている間に退位されたのか?
2024.12.26 12:00

ほぼ5分で読める勝共理論 61
天皇について⑨
上皇陛下はなぜ生きている間に退位されたのか?
編集部編
退位を決意されたやむを得ない理由
今回は、天皇についての9回目、最終回です。
前回少し説明しましたが、上皇陛下は8年前(2016年)の8月8日、退位の意向を自らお話しされました。
これは大変な決断でした。
何しろ当時の法律では、天皇が生きている間に退位することは許されていませんでした。
もし天皇の考えで法律ができたら象徴天皇としての原則に反してしまいます。しかしそれでもなお、上皇陛下が退位を決断し、その思いを発表したのにはやむを得ない理由がありました。
それはいったいどんな理由だったのでしょうか。
陛下のお言葉の抜粋です。
---
即位以来、私は国事行為を行うとともに、日本国憲法下で象徴と位置付けられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました。
何年か前のことになりますが、2度の外科手術を受け、加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から、これから先、従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが、国にとり、国民にとり、また、私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき、考えるようになりました。
私が天皇の位に就いてから、ほぼ28年、この間私は、わが国における多くの喜びの時、また悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事に当たっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。
皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行ってきたほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。
天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにもさまざまな影響が及ぶことが懸念されます。
始めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で、このたびわが国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相携えてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。
---
天皇の祈り
上皇陛下は、象徴天皇の在り方を自ら模索し、その務めを全身全霊で果たしてきたと語られました。
そして国民の幸福を祈る上で、国民の父母のようにして全国の人々と接してきたことがとても大きかったと語られました。
しかしご高齢になられ、これ以上健康を損なうと、社会が停滞し、国民の暮らしに影響を与えると考えられました。
これが、上皇陛下がお気持ちを発表された理由です。
天皇の祈りがなくなってしまうと、国家国民に影響が出ると考えられたのです。
安倍政権ではこの陛下の思いに応えて、陛下のお言葉によってではなくて、国民自らが陛下のお気持ちを察して法律を改正したというスタンスにしました。
これはとても重要な配慮だったと思います。
ただし、以前に説明したように、皇室の制度を安定して継続させていくためにはまだ改革が必要です。
筆者はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の支配下に生じたこの問題が解決されてこそ、日本の戦後が真の意味で終わるのではないかと思っています。
さあ、これで天皇についてのシリーズは終わりです。
皆さん、天皇について、理解は深まったでしょうか。
【関連書籍】
◆『よくわかる勝共理論~日本と世界の平和のために~』(光言社)