スマホで立ち読み 第28弾!
『拉致監禁』24
痛哭と絶望を超えて
2023.10.18 05:00
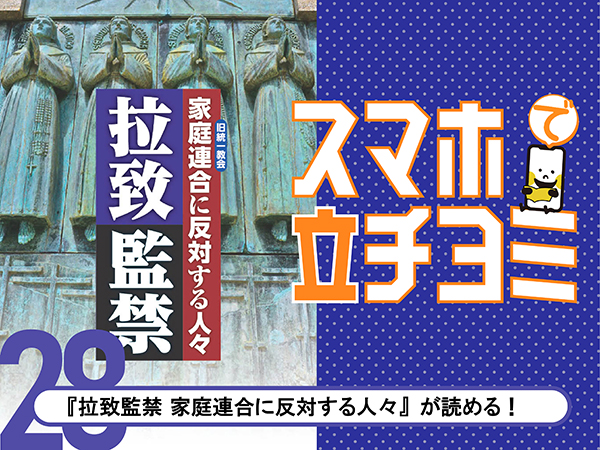
スマホで立ち読み Vol.28
『拉致監禁』24
世界平和統一家庭連合 総務局/編
スマホで立ち読み第28弾、『拉致監禁』を毎日朝5時にお届けします。
本書は現在の報道の背景を理解するとともに、拉致監禁の再発を防ぐために作成された一冊です。ぜひお読みください。
---
第二章 痛哭と絶望を超えて
序
2000年1月12日、新潟県柏崎市のS宅で、毛布にくるまった一人の女性(当時19歳)が保護されました。この女性は、小学校4年生の時の1990年11月13日の下校途中に拉致監禁され、犯人の自宅に連れ込まれていました。女性は、実に9年2カ月ぶりに家族と再会できたのです。この事件が発覚した時は、新聞やテレビがセンセーショナルに報じたので、記憶されている人も多いことでしょう。犯人のSには、懲役14年の刑が言い渡されています。
この女性の恐怖と絶望は、いかばかりだったでしょうか。また、解放された後もなお、リハビリの道は厳しいものになると想像しますが、家庭連合(旧統一教会)信者で拉致監禁をされた経験を持つMさんは、自身のホームページで新潟事件に言及し、こう語っています。
〈新潟の監禁事件は「いつか親が助けに来てくれる」。そういった希望が(監禁中に)あっただけ(まだ)よかったと、羨ましくなり涙が溢(あふ)れてくる。自分の監禁時のことを思い出すと監禁したのが親であり、兄弟も親戚もそれを容認していた。当然警察も助けてなどくれない。
一生ここから出られないという絶望感だけがあった〉
(米本和広著『我らの不快な隣人』情報センター出版局、120ページ)
拉致監禁の悲惨さは、ここにあります。Mさんは、監禁から解放されて十数年たっても、依然として後遺症に苦しみ、薬を飲んでいます。
また、このMさんとは別に、拉致監禁された家庭連合信者のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療に当たった医師は、「臨床精神医学」2000年10月号で、被害者の「家族のしたことは忘れられません。親から籍を抜きたいと思います」という言葉を紹介しました。事件から随分と時間が経過した後も、親に対して、“決して許せない”という感情を抱いているといいます。
親の存在なくして、私たちはこの世に存在できません。この親子の愛情の絆(きずな)をズタズタに切断させてしまうのが拉致監禁です。ほとんどの拉致監禁被害者は、その後、親との関係修復に苦悩しています。
本章では、家庭連合信者に対する拉致監禁、強制棄教事件の被害に遭われた方々の証言を取り上げます。これを通して、反対派が「救出」や「保護」と称する行為が、いかに被害者の人生に消えることのない深刻な傷跡を残してきたかを見ていきます。
---
次回は、「警察庁長官に訴えるも届かず」をお届けします。
◆「一気に読んでしまいたい!」というあなたへ
『拉致監禁: 家庭連合(旧統一教会)に反対する人々』を書籍でご覧になりたいかたは、コチラから
★「我々の視点」脱会説得による悲劇①
★「拉致監禁」問題を考える特別シンポジウム(2023年9月10日)ダイジェスト映像



