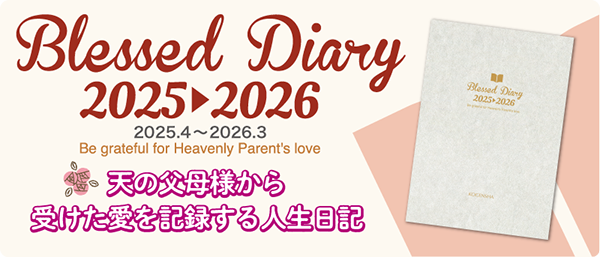誤解されたイエスの福音 24
死とは
2025.03.28 12:00
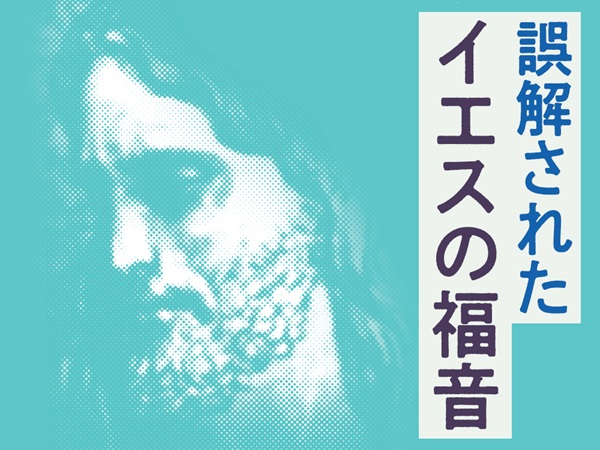
誤解されたイエスの福音 24
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「誤解されたイエスの福音」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
パウロのイエス観は果たして正しかったのか。イエス・キリストの再臨期を迎えた今、聖書の記述をもとに徹底検証します。
野村健二・著
第二章 イエスの本来の使命
五、イエスの復活をめぐって
死とは
文鮮明(ムン・ソンミョン)師は、人が罪を犯さなければ肉身が永存するなどというのは全くのナンセンスだと言われ、「皆さんがいくら『死なない』と言っても、死ぬ時になれば死ぬのです」(『天聖経』「地上生活と霊界」578頁)と片付けておられます。(実際、不死を信じたパウロも多分紀元64年、ローマ皇帝ネロの時に殉教の死を遂げました。)
どうしてそうなるかといえば、人間の肉身は、神が「かたち」を持ち、子女を繁殖させるためのもので、その用が済めば土に帰り、「霊人体」が霊界に行くように創られている。そのため、「腹中の水の世界、地上の地球星世界」、最後には「天上の空中世界」で暮らすというように、水中・地上・天上の三段階で人間が完成するように神が創造されたからなのだというのです(『天聖経』「地上生活と霊界」581頁)。
「水中」の胎児はへそで栄養を取っていますが、出産によって「地上」に出て来るときにはそのへその緒を切り取らなければならないので、胎児は死ぬ思いをしますが、地上に来てみれば、その代わりを口が務めるようになります。
それと同様に、「天上」(霊界)に行くときには、誰しも肉身を捨てなければなりません。そのために人間は大変な恐怖を覚える(パウロはそのため「罪の支払う報酬は死である」〈ローマ6・23〉と言い、永生の教義が多くの人の心を捉えた)。しかし、肉体の死後には誰でも例外なしに霊人体が働き出すので、実は何でもないのです。
---
次回は、「パウロの信仰義認の矛盾」をお届けします。
◆『誤解されたイエスの福音』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ