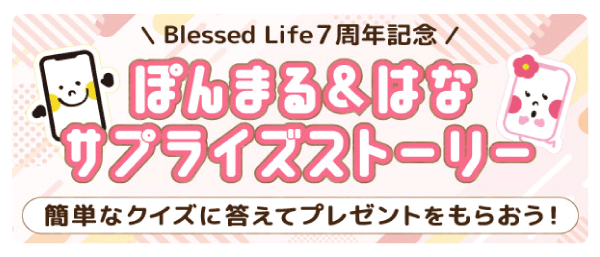誤解されたイエスの福音 21
“第二次摂理”への悲愴な決意
2025.03.07 12:00
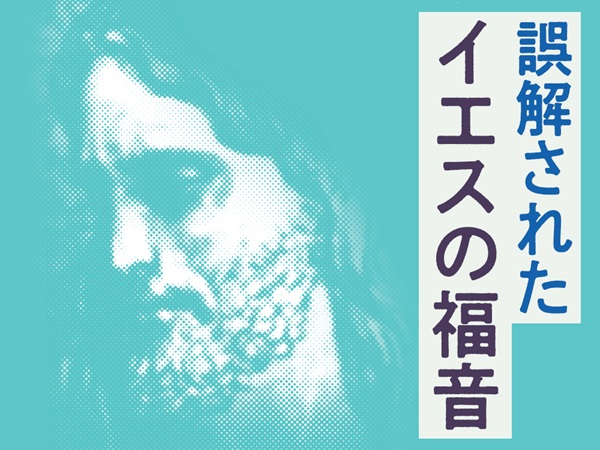
誤解されたイエスの福音 21
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「誤解されたイエスの福音」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
パウロのイエス観は果たして正しかったのか。イエス・キリストの再臨期を迎えた今、聖書の記述をもとに徹底検証します。
野村健二・著
第二章 イエスの本来の使命
四、窮地に追いつめられていくイエス
“第二次摂理”への悲愴(ひそう)な決意
これらの諸点から考えれば分かるように、ザカリヤ家庭の洗礼ヨハネ、ヨセフ家庭のマリヤ、ヨセフらの摂理に対する無自覚、無理解によって、神の第一次摂理である天国実現は全く実現不可能となりました。この第一次摂理の遂行のためには、一方においてユダヤの指導層——「長老、祭司長、律法学者たち」(マタイ16・21)——を動かし、他方においては「ユダヤの全土」からヨハネのバプテスマを受けるために続々と繰り出していた「エルサレムの全住民」(マルコ1・5)に働きかける必要がありましたが、その望みは洗礼ヨハネのエリヤの使命否定(ヨハネ1・21)によって全面的に崩壊し、神の子孫をつくるための洗礼ヨハネの妹との結婚という摂理も、マリヤの無自覚と怠慢のためにこれまた実現不可能となりました。
しかし、こうした八方塞(ふさ)がりの中にあってもイエスは決して摂理遂行をあきらめませんでした。イエスは一転して社会の最下層、「食をむさぼる者、大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間」(マタイ11・19、ルカ7・34)、さらには漁師(ルカ5・5〜11)や遊女(ルカ7・37〜38など)といった人々に働きかけて新しく弟子にされました。
そういう下層民の漁師であったシモン・ペテロが、イエスの「わたしをだれと言うか」という問いに対して「あなたこそ、生ける神の子キリストです」と答えると、この上なく喜ばれ、そう気づかせたのは天の父であると言われ、「わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう」と言われます。その一方では、その気づきが摂理の妨げになってはと心配され、「自分がキリストであることをだれにも言ってはいけないと、弟子たちを戒められ」(マタイ16・15〜20)、その後、十字架の道への摂理変更を口にされるようになったと言われます(同16・21)。
また、新しい十字架への道に赴(おもむ)くためエルサレムへと上って行かれたときには、そのイエスの姿を見て、こういう下層民の「大ぜいの弟子たちはみな喜んで、彼らが見たすべての力あるみわざについて、声高らかに神をさんびして言いはじめた、『主の御名によってきたる王に、祝福あれ……』」(ルカ19・37〜38)。イエスはこの行為をとがめたパリサイ人たちに対して、決然と「あなたがたに言うが、もしこの人たちが黙れば、石が叫ぶであろう」と言われます(ルカ19・39〜40)。
さらに、「いよいよ都の近くにきて、それが見えたとき、そのために泣いて言われた、『もしおまえも、この日に、平和をもたらす道を知ってさえいたら……しかし、それは今おまえの目に隠されている。いつかは、敵が周囲に塁を築き、……おまえとその内にいる子らとを打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来るであろう。それは、おまえが神のおとずれの時を知らないでいたからである』」(ルカ19・41〜44)という記述がその後に続きます。
これらの記述から、イエスの歩まれた道が神の立場から見てどのようなものであったのか、いっそう具体的に分かってくるのではないでしょうか。
第一弟子の漁師ペテロの「キリスト認知」の記述からは、神の第一次摂理はユダヤ民族にイエスをキリストと分からせることであって、そのために神は洗礼ヨハネを先触れとして送られたが、ヨハネのエリヤの使命否定の証言によって一転してそれが極めて難しくなったことから、漁師という下層民のペテロのキリスト認知を絶賛し、その一方では、イエスが「キリスト」だと自称していることがユダヤの上層部に分かれば厳しい弾圧を受けて、天国の実現どころか楽園をもたらすことさえも不可能となりそうな事態となったために、イエスがキリストだとは言うなと厳命されたのです。すなわち、天国実現は今は無理なので、ともかくも楽園を確保し、十字架→復活→再臨という迂回路で天国に至るという第二次摂理に転じることを、ここで決意せざるをえなくなったということがはっきりと分かります。
次の、主の送られた「王」と大ぜいの弟子たちが賛美したという記述からは、「キリスト」とは「王」にほかならず、ユダヤ人すべてがイエスを王として歓迎して迎えるようにすることが神の第一次摂理であったこと。それに対してパリサイ人が非難したのは、彼ら上層部がイエスを神の送った王であることを認めなかったということ。それに対して、イエスが、彼らが黙れば「石が叫ぶ」と言われたのは、イエスを上層部が本来の摂理が分からずにいかに弾圧しようとも、楽園実現の第二次摂理だけは命懸けでやり遂げるというイエスの決意を示したものだといえます。
最後の、ユダヤ人たちが「この日に、平和をもたらす道を知ってさえいたら」と嘆かれたという記述は、ユダヤ人が上層も下層もすべてがこぞってイエスを「キリスト」、「真の愛の王」として認めるようになるという神の第一次摂理こそが「平和をもたらす道」であったということを示すものだと言えるでしょう。イエスが「知ってさえいたら」と言われる以上、そういう「道」を神が着々と準備されていたことは間違いありません。実際、ユダヤ全土がイエスをキリスト(メシヤ)、王と認め、イエスを送った神への信仰によって団結したなら、当時ユダヤを治めていたヘロデ王もどうすることもできず、ユダヤは独立し、上述のごとく、神がBC5世紀ごろから一斉に準備されていた仏教、儒教、道教、ギリシャ哲学などの信仰的・思想的基盤を土台として、イエスがユダヤを基盤として全世界をみ言(ことば)と愛をもって統治されるようになっていたことは疑う余地がありません。
しかし、洗礼ヨハネのエリヤの使命否定によってこの第一次摂理は崩壊し、神の愛の支配を好まず、自分の利益や権力を増大させることばかりを考える神の敵、サタンの惑わしによって、一転してユダヤの上層はイエスをにせキリストとして嘲笑、非難、迫害し、ついにはイエスを十字架へと追い立てていくわけです。これは神のアブラハム以来2000年にわたる筆舌に尽くしがたい努力のすべてを水泡に帰させる行為で、その罪の大きさは計り知れません。そこでイエスは「城内の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来る」と預言されたとしか考えられません。
実際、AD73年、ローマの支配に反抗して民衆蜂起(ほうき)したユダヤの要塞マサダは陥落し、さらにそれ以後、ユダヤ人は祖国を失って流浪の民となりました。イエスの預言は完全に的中したのです。パウロがこのイエスの預言を知っていたならどう説明したのでしょう。十字架が初めからの神の予定であったのなら、その予定どおりを行ったユダヤ人たちがこんなひどい目に遭うはずはないではありませんか。
何度も言うように、十字架は神の第一次摂理ではなく、ユダヤ人が神の意志に全面的に背く場合に備えて、それでも神の摂理が無に帰することなく、天国実現は無理でも楽園だけは確立し、後はキリスト・イエス再臨の時に委(ゆだ)ねようという第二次摂理であったことは、このユダヤの崩壊という事実から見ても疑うことはできないのです。
---
次回は、「第二次摂理のシナリオ——十字架刑へ」をお届けします。
◆『誤解されたイエスの福音』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ