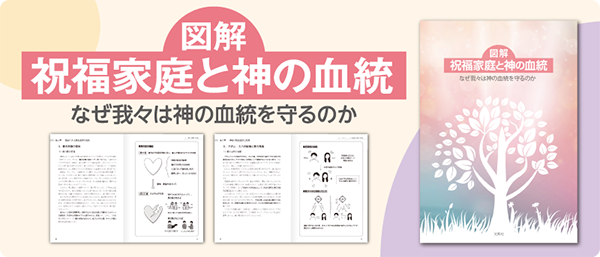女性の立場から見たレダ 14
1800家庭の世界宣教の苦労がレダ摂理に還元
2025.02.26 17:00
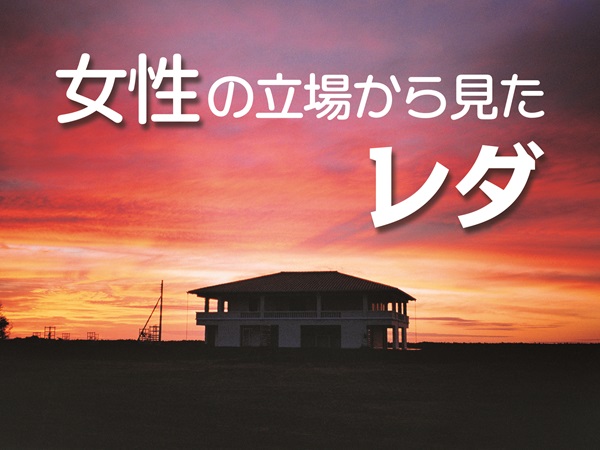
女性の立場から見たレダ 14
『世界家庭』に掲載された飯野絢子(あやこ)さんの証しを、毎週水曜日配信(予定)でお届けします。
飯野貞夫・天一国特別巡回師(777家庭)の夫人・絢子さん(2024年10月聖和、享年86)は、飯野巡回師と共に2008年から4年間にわたってレダ(パラグアイ)に滞在し、開拓にいそしむ日本人国家メシヤたちを支えました。そんな絢子夫人のレダでの歩みを紹介します。

1800家庭の世界宣教の苦労がレダ摂理に還元
2002年、2006年、2008年から2012年までの期間、レダにあって共に汗したかたがたへの思いは、私にとって特別です。「蕩減(とうげん)原則は現地においてなされる」(1999年9月23日、オリンポ)というレダ出発時のみ言があります。現地という意識があれば、どこにいてもそこはレダそのもの、現地そのものになるのです。日本での支援を担当する国家メシヤ家庭は、食費も削るような生活の中で責任を果たすための努力を惜しみませんでした。
17年にわたってレダを指揮してきた双璧は、中田実さん(ハンガリー国家メシヤ、777家庭)と上山貞和さん(スペイン国家メシヤ、777家庭)です。中田さんは子供の頃からアレルギー体質で、草木にかぶれるため、遠足にも行けなかったそうですが、北海道入植者の三代目として、開拓に向かう揺るぎない信念で取り組んできました。また上山さんも、血圧を下げる薬を常用しながら闘ってきました。
心臓の手術をした身で、2009年に1年間応援に来てくれた大滝順治さん(カタール国家メシヤ、777家庭)を、「レダで、もしものことがあったら……」と、式服を持たせて送り出した妻・ヒロ子さんの貴い心根。レダ開拓10周年の式典に夫婦で参加した鈴木京一さん(アルメニア国家メシヤ、74家庭)が、かつて自分が汗したレダの敷地内を、妻・真知子さんの手を取りながら案内していた麗しい姿。真の父母様に寄せる熱い心情を持ってレダで励む夫・藤原秀敏さん(クロアチア国家メシヤ、777家庭)を、日本で見守り続けた妻の淑香さんの精誠(2016年7月に藤原さんは淑香さんをレダに案内しました)。
2009年11月、突然、中田欣宏さん(ラトビア国家メシヤ、777家庭)の夫人・育子さんの聖和の報がレダに入りました。瞬間、「私の身代わりで逝った」と直感するものがありました。レダの深刻な状況を背負ってくださったとしか考えられません。良き妻であり、良き母、そして孝の人でした。
またレダ摂理は、1800家庭の協力なしには絶対に成しえなかったと痛感しています。
「1800というのは何を意味するのか? 六数はサタン数であるが、その六数に、六数に、六数をプラスした十八数、これを象徴する。これはサタン世界を制圧するという意味である。完全に制圧する」(「歴史の転換点」1975年12月1日、ニューヨーク・ベルベディア)
1800家庭の祝福と同時に世界中に宣教師として派遣され、任地国に定住することもできず転々とし、投獄、時には殉教にも至る歩みを甘受してかちえたもの全てが、レダ摂理に還元されていると確信するのです。
かつてパラグアイ宣教師として歩み、今もパラグアイの教会でその苦労が語り継がれ、慕われている西脇徹さん(アゼルバイジャン国家メシヤ、2012年12月聖和)。開拓の初めからレダに入り、その温厚な人柄で兄弟たちの潤滑油となった戸石文夫さん(ジブチ国家メシヤ)。ベネズエラ宣教師時代に培ったスペイン語の力を駆使し、2000年から始まった国際協力青年奉仕隊の受け入れに責任を持ってきた三石昭治さん(サモア国家メシヤ)。
電気関係のプロで、写真の腕前はピカイチ、作詞作曲なども手がける、感性豊かな小田文雄さん(チュニジア国家メシヤ)は、心臓の大手術をした体で貢献してきました。また、当時、機械全般を担当していた金子哲太さん(コンゴ民主共和国国家メシヤ)は、任地国の重い蕩減をかけて身を打ちながら汗していました。
夫人たちの精誠も忘れられません。スペイン語に精通していた岩澤正子さん(モーリシャス国家メシヤ)と青木悦子さん(ロシア国家メシヤ、1800家庭)は、来園のたびに、現地の労働者たちとの橋渡しをしてくれました。
皆、愛すべき1800家庭の弟妹たちです。
そして何よりも、長期滞在者の妻たちの、気丈でけなげな献身は、神様が直接主管されるものと思います。ここで全員を紹介することはできませんが、神様は全ての国家メシヤの精誠を覚えておられると信じます。このような国家メシヤの歩みを思うにつけ、全家庭の列伝を著したい思いに駆られます。
真のお父様はこう語っておられます。「生涯、神様と焦点を合わせて生きようと努力してきた。死を覚悟して一生を神様と焦点を合わせて生きようとしてきた。あなたたちがその100分の1でも神様、あるいはお父様と焦点を合わせて生きようと努力するだけでも、あなたたちは困難を免れることができるだろう」(2008年6月13日、天正宮〈チョンヂョングン〉博物館)
私はルカによる福音書第24章13節のエマオへの道のくだりがとても好きなのですが、このみ言はその場面を思い起こさせるものです。イエス様の死後、失意のうちに故郷のエマオに向かう2人の弟子に、復活したイエス様が現れるのですが、彼らは気がつかないのです。神様、真の父母様と「焦点を合わせて」生きることの大切さを痛感させられる聖句です。
「心情の世界は、誰でも満点に授かっている。……先生を慕う。何で慕うか。その主体の要因を分けてもらうために慕うんだよ。先生はそういうような無限の神につながった愛があるんだよ。分けてやってもやっても限りないくらいある」(「刺激について」1970年11月26日、水澤里〈ステンニ〉)というみ言は希望です。
(続く)
---
次回は、「お父様に養殖のパクーを一口でも食べていただきたかった」をお届けします。