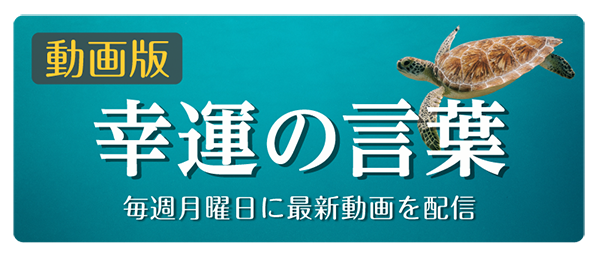青少年事情と教育を考える 283
次の学習指導要領、ポイントは「教員の負担軽減」
2025.01.10 17:00

青少年事情と教育を考える 283
次の学習指導要領、ポイントは「教員の負担軽減」
ナビゲーター:中田 孝誠
学習指導要領の改訂に向けた議論が始まります。
学習指導要領は、全国どこの学校でも一定水準の教育が受けられるよう、国が定めている教育の基準です。各学校では、学習指導要領に示された教育目標や指導内容をもとに、地域や子供たちの状況に即して授業を行います。
この学習指導要領は、社会状況の変化などを踏まえて10年に1回程度改訂されます。
現在の学習指導要領は、2017~18年に改訂され、2020〜22年度から実施されています。つまり次の学習指導要領は、2030〜40年代を生きる子供たちの教育指針になるわけです。

改訂の際は文科相から中央教育審議会(中教審)に諮問されますが、それが昨年12月に行われました。
次の学習指導要領をどのような内容にするか。本格的な議論はこれから始まりますが、改訂に当たって大きなポイントになると見られているのが、教員の負担軽減です。
中教審への諮問では、今後の審議事項として「質の高い、深い学び」や「多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程」、「教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯(しんし)に向き合う」といった項目が示されています。
そして、これらの中に「新たな時代にふさわしい学びや教師の指導性」「教師に『余白』を生み、教育の質の向上に資する…柔軟な教育課程編成」といった項目が挙げられ、具体的に標準授業時数や年間の最低授業時数を柔軟に決められるようにすることを検討課題にしています。
さらに、教育課程の実施に伴う過度な負担が生じにくくすることや、年間の標準総授業時数を増加させないこと、情報技術などの分野で教師の負担軽減を図ることなどもうたっています。
教育課程の負担や授業時数の軽減は、教員はもちろん、不登校の児童生徒の増加への対応ともいわれています。
日本の学校教育は国際的に高く評価されていますが、その要因として教員が大きな役割を果たしてきました。一方で教員の大きな負担が問題になっています。
次の学習指導要領は、教員の負担を軽減しつつ、子供たちの質の高い学びを進めるための方向性を示そうというわけです。