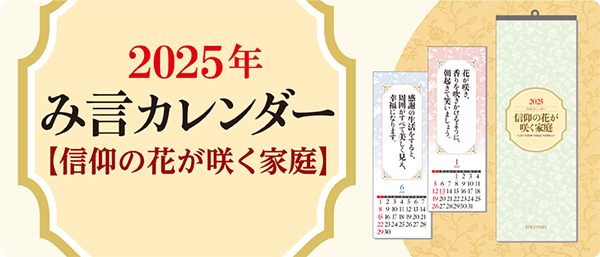青少年事情と教育を考える 282
いじめと思春期の「愛着」
2024.11.29 17:00

青少年事情と教育を考える 282
いじめと思春期の「愛着」
ナビゲーター:中田 孝誠
前回に続き、文部科学省が公表した「生徒指導上の諸課題に関する調査」を取り上げます。
今回はいじめについて考えます。
昨年度(2023年度)、全国の小・中・高・特別支援学校でのいじめの認知件数は73万2568件で、前年度から5万620件増え、過去最多となりました。
校種別に見ると、小学校が58万8930件(前年度比3万6986件増)で全体の約8割を占めています。中学校が12万2703件(同1万1299件増)、高校が1万7611件(同2043件増)、特別支援学校が3324件(同292件増)でした。
このうち、パソコンや携帯電話を使ったいじめは2万4678件(同758件増)、重大事態(いじめ防止対策推進法に規定されています)だったのは1306件(同387件増)です。
また、全体の件数の中で、現在は「解消している」ものが77.5%でした。

こうした状況に対して、政府の「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」は、次のような対策に重点を置いて取り組むとしています。
一つは、いじめ未然防止教育のモデルを構築し、指導案や指導教材等を作成する。
また、いじめの質的分析のための専門家会議の新設や、子供の視点に立った相談体制の充実(1人1台端末などの活用による「心の健康観察」の導入など)です。
さらに、加害児童生徒への対応の強化、ネットいじめ対策も強化するとしています。
一方で、政府や自治体の対策では取り上げるのは難しいですが、家庭での親子関係の影響なども考慮する必要があると思われます。
例えば、「愛着」という観点から見ると、「仲間指向性」という現象が起こっているというのです(小野善郎『思春期の子どもと親の関係性』福村出版)。
子供の精神医学の専門医である小野氏によると、愛着は親や信頼できる大人との間で築かれるもので、親は子供を保護し、安心感を与え、コンパスのように正しい方向性を示す役割があります。それによって子供は安心して外の世界に出ていけるというわけです。
しかし、ここで言う「仲間指向性」は、親や信頼できる大人に代わって友達を愛着の対象にしてしまうというものです。
友達関係は子供の成長にとって重要ですが、思春期は人間として成熟していない不安定な状態です。
親子関係では世話と保護をする親と、依存する子供という関係性がありますが、お互いに未熟な友達との関係ではそれが難しく、かえって対等であるはずの関係性の中に支配する側と依存する側という序列を生み、時には凶悪な行動に及んでしまうというのです。
小野氏は「いじめは大人への愛着を失った子ども集団の中で起きる仲間指向性による行動として理解することができる」と指摘します。そして親に対して、子供への愛着を残して安全基地となって、親で在り続ける努力をしてほしいと強調しています。
もちろん、いじめの原因は愛着の問題だけではなく、複雑な要因があります。その中で政府や自治体が取り組む対策とともに、学校での友人関係と家庭での親子関係に注目する必要があると考えます。