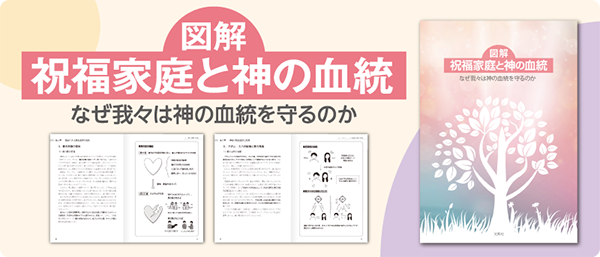女性の立場から見たレダ 7
真心さえあれば、言葉は不足でも気持ちは通じる
2025.01.08 17:00
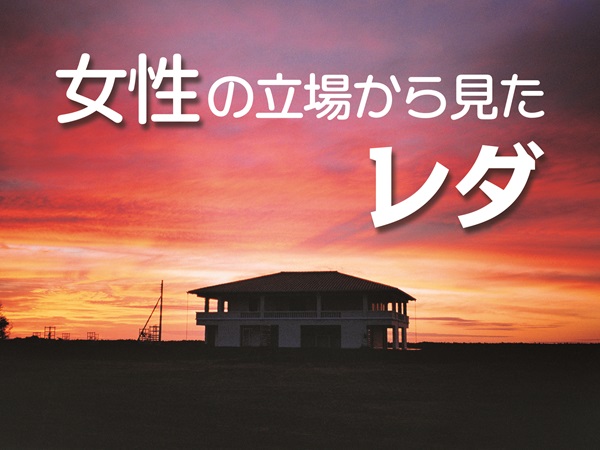
女性の立場から見たレダ 7
『世界家庭』に掲載された飯野絢子(あやこ)さんの証しを、毎週水曜日配信(予定)でお届けします。
飯野貞夫・天一国特別巡回師(777家庭)の夫人・絢子さん(2024年10月聖和、享年86)は、飯野巡回師と共に2008年から4年間にわたってレダ(パラグアイ)に滞在し、開拓にいそしむ日本人国家メシヤたちを支えました。そんな絢子夫人のレダでの歩みを紹介します。

真心さえあれば、言葉は不足でも気持ちは通じる(前)
パラグアイでは、首都のアスンシオンでさえ、インディヘナには仕事が限られているというのに、レダには男性だけでなく女性の仕事もあるということで、みんなが働きに来たがりました。賃金は最低基準でしたが、三食肉が食べられ、給料も遅れたことはありませんでしたから。
時々、インディヘナの村に住む人たちから私にコイマ(袖の下)が届きました。カゴやうちわといった手作りの民芸品に添えた短いメッセージを、仕事に来る女性たちに託して、自分も雇ってほしいというさりげないアピールをしてくるのです。佐野道准さん(チリ国家メシヤ、1800家庭)は面白がって、よく私をからかいました。「ワイロですよ、ワイロ!」と。
ただ、雇用契約をするに当たっては、レダ「ムーンチャーチ」としての約束事がありました。「男女問題を起こさない」「酒を飲まない」「賭け事をしない」「盗まない」の四つです。そして、それを守ると約束した人だけを雇っていました。
インディへナの人たちはとても誇り高く、純朴で気持ちの良い人が多いのですが、教育の面では遅れています。レダやオリンポのあるチャコ地方は国も顧みないような未開の地域なのですが、そこの出身のある女性(23歳)は文字が書けず、給料の受け取り書にサインができませんでした。21世紀に自分の名前すら書けない人がいるのかと驚くとともに、真の父母様が願われる「平準化」への道のりの険しさを実感しました。


また、道徳や規範の面でも、大いに教育が必要でした。
マグカップやフォークなど、小さな物がなくなるのはごく普通。ビデオデッキや洗濯機、モーターなどの電化製品も消えます。彼らは見事な連係プレーで、大きな物でも上手に持ち出すのです。村には電気がないのに、それをどうするのかと思っていたら、売るという方法があるのです。レダから船でパラグアイ川を4時間ほど下った所にあるオリンポの道端で、レダ修練所のスリーピングバッグが売り出されていたこともありました。
また、少しでも長く働きたいので、同僚が病気だとうそをついて、代わりに納まろうとする人もいました。「あの人と組みたくない」など、不満も絶えませんでした。
そういうことに対しても、通訳を通して話をじっくり聞きながら、一つ一つ向き合っていきました。注意することはたくさんありましたが、自分のためを思っての叱責だと分かれば、しこりになることはありませんでした。真心さえあれば、言葉は不足でも気持ちは通じることを実感しました。
それでも、問題はしょっちゅう起こりました。酒は隠れて飲み、サッカーを楽しんでいるかと思えば、賭けサッカーだったなど。男女問題も起こします。問題が発覚した場合は、即座にボートに乗せて、村に送り返していました。
(続く)
---
次回は、「日本ではありふれた食べ物でもレダでは『金曜日の幸せ』」をお届けします。