誤解されたイエスの福音 7
十字架は神の予定か
2024.11.29 12:00
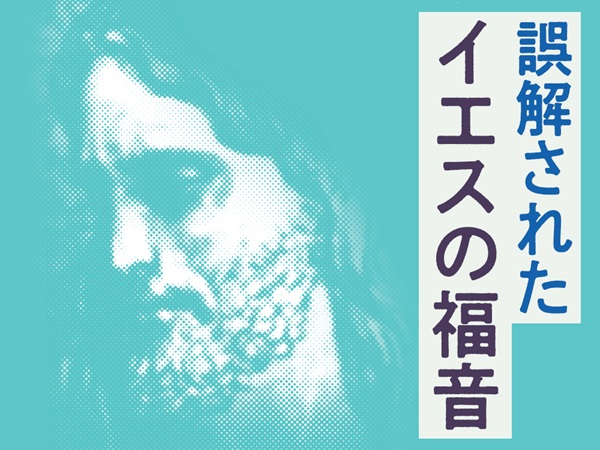
誤解されたイエスの福音 7
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「誤解されたイエスの福音」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
パウロのイエス観は果たして正しかったのか。イエス・キリストの再臨期を迎えた今、聖書の記述をもとに徹底検証します。
野村健二・著
第二章 イエスの本来の使命
一、十字架は神の予定か
パウロは「十字架につけられたキリスト」ということ以外には何も知る必要がないという思い込みから、使徒たちから肝心のイエス自身の福音について積極的に聞こうとせず、自分の受け取り方についてチェックもしてもらわないまま、独断で次のような教義(十字架贖罪〈しょくざい〉論)を編(あ)み出してくるのです。
「すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなって」いる(ローマ3・23)。
そこで、「時の満ちるに及んで、神は御子(みこ)を女から生れさせ、……律法の下(もと)にある者をあがない出すため、わたしたちに子たる身分を授けるため」に「おつかわしになった」(ガラテヤ4・4〜5)。
「神はこのキリストを立てて、その血による、信仰をもって受くべきあがないの供え物とされた。それは神の義を示すためであった」(ローマ3・25)。
「キリストは、すべて信じる者に義を得させるために、律法の終りとなられたのである」(ローマ10・4)。
したがって、だれでも「自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる」(ローマ10・9)
「それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこにはなんらの差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは、価なしに、神の恵みにより、キリスト・イエスによるあがないによって義とされるのである」(ローマ3・22〜24)。
要約すれば、
①すべての人は罪を犯しているので、律法によっては義とされえない。
②そこで神はイエスをそれらの罪を代わりに償わせるために生まれさせ、十字架で血を流して死なせ、その後、神によってよみがえらせることをもって、あがなうことにされた。
③だから、そのことを信じ、イエスこそそのような役割を果たされる「主」だと告白しさえすれば、どんな悪いことをした人でも、差別することなしに救われる。
このように「神の義が、律法とは別に、しかも律法と預言者とによってあかしされて、現された」(ローマ3・21)というのです。
こんなことを言い聞かせられれば、罪を犯したという覚えのある者、ユダヤ人で律法を守れなかったという負い目を感じている者はみな跳び上がって喜び、争ってイエスこそそういう力を与えられた主だと告白する気になることでしょう。
しかし、肝心のイエスご自身がこんなことを宣言し、あかしされたという確かな証拠がどこかにあるのでしょうか。それが問題です。
まず、「イエスは主である」という信仰告白について、イエスご自身は「山上の垂訓」の中で、はっきりとこう言っておられます。
「わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいるのではなく、ただ、天にいますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである(太字は筆者)」(マタイ7・21)
次に、「律法の効力」──イエスの十字架上の死が「律法の終り」をもたらし、律法とは別に新しい「神の義」が現れるなどということがありうるのかという問題については、やはり「山上の垂訓」の中でイエスはこう明言しておられます。
「天地が滅び行くまでは、律法の一点、一画もすたることはなく、ことごとく全うされる(太字は筆者)……それだから、これらの最も小さいいましめの一つでも破り、またそうするように人に教えたりする者は、天国で最も小さい者と呼ばれるであろう。しかし、これをおこないまたそう教える者は、天国で大いなる者と呼ばれるであろう」(マタイ5・18〜19)
ここで、イエスははっきりと「天地が滅び行くまでは」と断っておられます。実際、イエスが十字架にかかったからといって、それ以後、天地が滅んでしまったでしょうか。律法は天地の秩序の維持のためにどうしても必要なものであるはずで、十字架によって、パウロのいう「律法の終り」が来るなどということはありえません。それどころかイエスは、逆に律法以上の道徳性を一般の聴衆に求めておられたのです。
例えば「あなたがたの義が律法学者やパリサイ人の義にまさっていなければ、決して天国に、はいることはできない」(同5・20)と説かれて、そうした新しい高い「義」の一例として、「だれでも、情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫(かんいん)をしたのである」(同5・28)、「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」(同5・44)など、極限ともいえるほどの高い道徳基準を示されたのです。
ここでパウロが勝手に唱え出した「信仰義認」の教義、「人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰による(太字は筆者)のである」(ローマ3・28)は、イエスの弟ヤコブが書いたと言われる「人が義とされるのは、行いによるのであって、信仰だけによるのではない(太字は筆者)」(ヤコブ2・24)と神学者の間で一般的によく比較され、ルターなどは後者を「わらの手紙」とこき下ろしたと言われますが、このヤコブの手紙はイエスの主張をそのまま述べているのであって、真に対立するのはパウロとヤコブではなく、パウロとイエスだと言わなければなりません(信仰ももちろん必要ですが、行為に現れる信仰でなければ、イエスは信仰と認めなかったのです)。
このように、パウロの十字架贖罪論は、イエスの「山上の垂訓」とほんの少し比較検討するだけでも数々の矛盾が露呈してきます。しかしこの十字架贖罪論は従来のキリスト教の根本的教義とされているものなので、これだけの吟味にとどめることなく、聖書全体の記述と照らし合わせて、これが妥当なものなのかどうかを根本的に検討してみることにしましょう。
---
次回は、「食い違う『メシヤ像』」をお届けします。
◆『誤解されたイエスの福音』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ



