誤解されたイエスの福音 6
パウロによるイエスの福音の軽視
2024.11.22 12:00
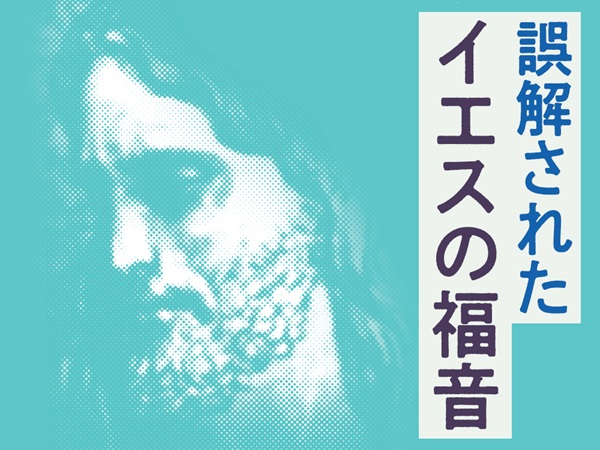
誤解されたイエスの福音 6
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「誤解されたイエスの福音」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
パウロのイエス観は果たして正しかったのか。イエス・キリストの再臨期を迎えた今、聖書の記述をもとに徹底検証します。
野村健二・著
第一章 イエスは神そのものか
二、パウロは生前のイエスの福音や行動を知っていたか
パウロによるイエスの福音の軽視
こういうことは考えたくないことですが、パウロはイエスが罪人(つみびと)たちを救うために十字架さえもいとわなかったという愛にだけ心を打たれ、その思想性に関してはほとんど着目せず、その教えを受けたペテロたち使徒も漁夫や取税人にすぎなかったため、ガマリエルの高弟である自分の学識と思考力とは全く比べものにならないとみくびっていたのではないでしょうか。
実際パウロは、「事実、わたしは、あの大使徒たちにいささかも劣ってはいないと思う。たとい弁舌はつたなくても、知識はそうでない」(コリントⅡ11・5〜6)、「たといわたしは取るに足りない者だとしても、あの大使徒たちにはなんら劣るところがない」(同12・11)と、その自負を隠すこともせず露骨に表明しています。
さらにイエスの一番弟子ペテロが、パウロ流の(異邦人にはユダヤ人の伝統を守ることを強いない)伝道方法に従わないからといって、自分がまるで主イエスででもあるかのように、ペテロを衆人の面前で叱りつけさえしているのです(ガラテヤ2・11〜14)。
このことは、ガラテヤ人への手紙の次のくだりを読むといっそうはっきりしてきます。
「その後3年たってから、わたしはケパ(ペテロ)をたずねてエルサレムに上り、彼のもとに15日間、滞在した。しかし、主の兄弟ヤコブ以外には、ほかのどの使徒にも会わなかった(太字は筆者)。ここに書いていることは、神のみまえで言うが、決して偽りではない」(ガラテヤ1・18〜20)。
すなわち、パウロは神に誓って、イエスの召命を受けてから足掛け3年たって、やっとエルサレムに行きはしたが、それでもペテロ以外にはイエスの兄弟ヤコブに会っただけで、そのほかの使徒にはだれとも会っていないと、誇らしげに宣言しているのです。これは会っても何にもならないと彼が思っていたことを証明するものではないでしょうか。これは使徒に対する無視である以上に、使徒を指導したイエスの思想(福音)に対するはなはだしい軽視といえるのではないでしょうか。
さらにコリント人への第一の手紙には、パウロが使徒たちからイエスについて何も聞こうとしなかった根本動機が明示されています。
「兄弟たちよ。わたしもまた、あなたがたの所に行ったとき、神のあかしを宣(の)べ伝えるのに、すぐれた言葉や知恵を用いなかった。なぜなら、わたしはイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことは、あなたがたの間では何も知るまいと、決心したからである(太字は筆者)」(コリントⅠ2・1〜2)。
すなわちパウロは、主であるイエス・キリストの十字架の贖罪(しょくざい)を信じさえすれば救われるのであって、そのほかにはいかなる神学的知識も知恵も必要ではないと考えたからこそ、使徒たちからイエス自身の教えや生活について何も知ろうとしなかったというのです。これは神の知恵──福音の重要性についての全面的否定であり、率直に言えば、非理性的な盲信だと言わなければなりません。
パウロによるイエスの福音の軽視、無視の程度がどれほどのものであったかについて、20世紀最高の聖書神学者の一人、ルドルフ・ブルトマン(1884〜1976)は、「パウロは主の言葉を二つしか引用していない(太字は筆者)」「主の言葉が期待されるべきところでも何も引用していないのを見れば、彼は現に引用されているもの以外に主の言葉を知らなかった(太字は筆者)ことがますますはっきりする」と言い(『ブルトマン著作集11』新教出版社、215〜216頁)、「パウロは、直接的にであれ最初の弟子たちの媒介を経てであれ、イエスの弟子ではなかった(太字は筆者)」(『ブルトマン著作集 8』同上、20頁)ということが、W・ヴレーデ(『パウロ』1905年)や、アルノルト・マイヤー(『イエスかパウロか』、原著Arnold Meyer,Wer hat das Christentum begr ündet,Jesus oder Paulus ? 1907S.95f. 1907年)から明らかになったとまで言っています。
マイヤーはこの中で、「キリスト教とはキリストを天的な神の子と信じる信仰であると考えるなら……そのようなキリスト教を創始したのは、主としてパウロ(太字は筆者)であって、イエスではない」とまで断定しているのです。
ブルトマンが指摘しているパウロが引用した二つの主の言葉とは、「妻は夫から別れてはいけない」(コリントⅠ7・10)と、「福音を宣べ伝えている者たちが福音によって生活すべきこと」(コリントⅠ9・14)ですが、それ以外に私自身が見いだしたもっと中心的な福音として、ローマ人への手紙13章9節とガラテヤ人への手紙5章14節に、どんな戒めも「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ」という言葉に帰するというイエスの指摘(マタイ22・39、マルコ12・31、ルカ10・27、使徒20・35)が、主の言葉だとは断らないままの形で示されています。
しかしこれも、福音書におけるイエスのみ言(ことば)の中では、律法の中で「第二」に大切な戒めとされており、「第一」に大切な戒めだと言われた肝心の「主なるあなたの神を愛せよ」は抜け落ちています。
してみると、パウロはこの最も中心的なイエスのみ言すらも正確には把握していなかったのではないかと勘ぐりたくなるのです。
こうした点から考えると、パウロがイエスを神と同一視してしまったのは、このような生前のイエスの言動についての無知と、イエスから受けた霊的召命という神秘体験から来るのではないかと思われてきます。
この著しいパウロによるイエスのみ言(福音)の軽視が、どのような結果を招いたか。そのことについて次に検討してみることにしましょう。
---
次回は、「十字架は神の予定か」をお届けします。
◆『誤解されたイエスの福音』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ



