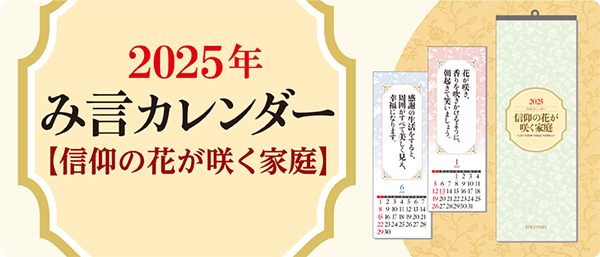誤解されたイエスの福音 5
パウロの来歴
2024.11.15 12:00
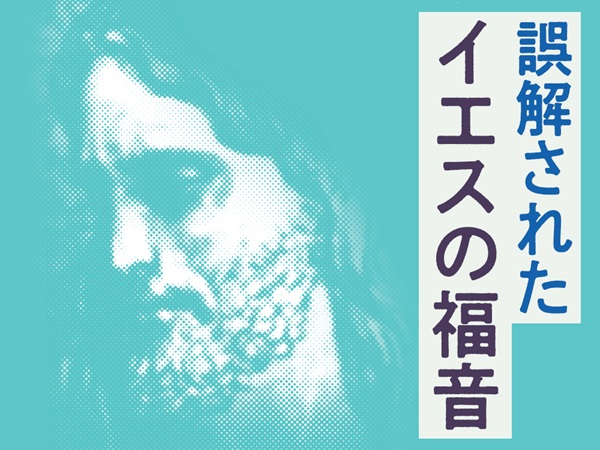
誤解されたイエスの福音 5
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「誤解されたイエスの福音」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
パウロのイエス観は果たして正しかったのか。イエス・キリストの再臨期を迎えた今、聖書の記述をもとに徹底検証します。
野村健二・著
第一章 イエスは神そのものか
二、パウロは生前のイエスの福音や行動を知っていたか
パウロの来歴
さて、ではパウロ(ヘブル語名でサウロ)はどうしてイエスを神と同一視するに至ったのでしょうか。そのことを理解するためには、パウロとはどういう来歴の人で、イエスとパウロとの関係はどのようなものであったかを明確にしておく必要があります。
パウロはイエスの生前からの弟子ではなく、イエスの死後に出現したキリスト教の初期には、キリスト教徒撲滅の最有力の中心人物として活躍した人物だったのです。
当時、使徒たち以上に活躍したステパノという布教者がいました。反対者たちがステパノと議論しましたが、太刀打ちできなかったので、民衆、長老、律法学者たちを煽動(せんどう)し、「彼を襲って捕(とら)えさせ、議会にひっぱってこさせた」(使徒6・10〜12)。その議会でステパノは、アブラハムに始まって、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ヨシュア、ダビデ、ソロモンと代々受け継がれてきたイスラエル(ユダヤ)民族の歴史について熱弁をふるい、あなたがたの先祖は代々の預言者をひとり残らず迫害し、「正しいかた(イエス)の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなたがたは、その正しいかたを裏切る者、また殺す者となった」(同7・52)と、その責任を問いました。そこでこれを聞いていた観衆は歯ぎしりして彼を市外に引き出し、みんなで石で打ち、ステパノは「この罪を彼らに負わせないでください」と大声で祈りつつ息を引き取るという事件が起こります。
そのとき、サウロはステパノを殺すことに賛成し、さらにその後、「家々に押し入って、男や女を引きずり出し、次々に獄に渡して、教会を荒し回った」(同8・3)と書かれています。
しかしそのとき、十字架の刑死によって霊界に行っていたと思われる(パウロはそのことを否定)イエスは、サウロが律法に通じ、ギリシャ語に優れ、ローマ市民権を持ち、抜群の指導力と、試練に屈しない精神力を持っているのを見て、「わたしの名を伝える器(うつわ)」(同9・15)だとこの上なく高く評価されたのでしょう。ステパノの殉教の死を代償(統一思想の用語では「蕩減(とうげん)条件」)として、あえて福音伝達の指導者(使徒)の一人として召し出されるのです。
「さてサウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息をはずませながら、……この道の者を見つけ次第、男女の別なく縛りあげて、……道を急いでダマスコの近くにきたとき、突然、天から光がさして、……『わたしは、あなたが迫害しているイエスである。さあ立って、町にはいって行きなさい。そうすれば、そこであなたのなすべき事が告げられるであろう』」(同9・1〜6)。こうイエスはサウロに呼びかけられます。
「サウロは地から起き上がって目を開いてみたが、何も見えなかった。そこで人々は、彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間、目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった」(同9・8〜9)。そこでイエスはその弟子アナニアに幻の中で現れて、サウロのもとに行かせ、「あなたが来る途中で現れた主イエス」が、「あなたが再び見えるようになるため、……聖霊に満たされるために、わたしをここにおつかわしになった」と伝えさせます。「するとたちどころに、サウロの目から、うろこのようなものが落ちて、元どおり見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマを受け、また食事をとって元気を取りもどした」(同9・17〜19)
その後、サウロはイエスから見込まれたとおり、「ただちに諸会堂でイエスのことを宣(の)べ伝え、このイエスこそ神の子であると説きはじめた」(同9・20)。これを聞いた人々はサウロの前歴をよく知っているので、みな驚き、非難します。「しかし、サウロはますます力が加わり、このイエスがキリストであることを論証して、ダマスコに住むユダヤ人たちを言い伏せた」(同9・22)。
そのため、「ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をし」、サウロは逆にエルサレムにまで行って「弟子たちの仲間に加わろうと努め」た。しかし弟子たちは彼を恐れて信じようとしないので、バルナバ(慰めの子)と呼ばれる、使徒以上の指導力と親切さを備えた弟子が、ほかの者に、サウロがイエスにどのように導かれることによって、イエスのことを大胆に宣べ伝えるようになったのかをよく説明した結果、「それ以来、彼は使徒たちの仲間に加わり、エルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合った」(同9・28〜29)。このように使徒行伝の著者ルカは書いています。
ここで問題なのは、その後、異邦人にとって親しみやすい「パウロ」というローマ名を名乗るようになった彼自身は、ルカの記述とは異なり、“エルサレムには行かなかった”と書いているということです。このことが今検討しているパウロの主張──イエスの素性(すじょう/神そのものであったかどうかということ)と後述の、神がイエスをこの世に送った動機についての説(十字架贖罪〈しょくざい〉論)の正しさを判断するに当たって、この上なく重大な問題となってくるのです。
パウロはこう書いています。
「ユダヤ教を信じていたころのわたし(パウロ)の行動については、あなたがたはすでによく聞いている。すなわち、わたしは激しく神の教会を迫害し、また荒しまわっていた。そして、同国人の中でわたしと同年配の多くの者にまさってユダヤ教に精進し、先祖たちの言伝えに対して、だれよりもはるかに熱心であった。ところが、母の胎内にある時からわたしを聖別し、み恵みをもってわたしをお召しになったかたが、異邦人の間に宣べ伝えさせるために、御子(みこ)をわたしの内に啓示して下さった時、わたしは直ちに、血肉にも相談せず、また先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも上らず、アラビヤに出て行った。それから再びダマスコに帰った」(ガラテヤ1・13〜17)。
この手紙から判断すると、どうやらパウロは自分がイエスから召命された理由は、
①ユダヤ教に、多くの者にまさって精進したこと
②先祖たちの言い伝えに対して熱心であったこと
③母の胎内から神が聖別し選んでくださっていたこと
によるもので、それだけでイエスの十字架の宣布者(使徒)の資格は十分であり、イエスから愛弟子として直接指導を受けた使徒たちを通して生前のイエスの教えを聴くためにエルサレムにまで上る必要はないと考えていたらしいと思われます。
パウロが指導を受けたガマリエルがどれほど卓越した律法学者であったかは分かりませんが、イエスが神の全使命を果たすことを任(まか)せられたキリスト(救世主)であるとすれば、当然ガマリエル以上の完全な教えを宣布されたはずだと、パウロは考えなかったのでしょうか。
パウロも、律法は「わたしたちをキリストに連れていく養育掛(がかり)」(ガラテヤ3・24)とは見ていたようですが、しかしそれは「信仰によって義とされるため」の養育掛としての低い教えであるにすぎず、律法よりもっと深く高い教えを当然イエスが説かれたであろうとは、残念ながら、パウロは思っていなかったようなのです。
実際、パウロはこう言っています。「わたしたちの知るところは一部分であり、預言するところも一部分にすぎない。全きものが来る時には、部分的なものはすたれる。わたしたちが幼な子であった時には、幼な子らしく語り、幼な子らしく感じ、また、幼な子らしく考えていた。……わたしたちは、今は、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。……わたしの知るところは、今は一部分にすぎない。しかしその時には、わたしが完全に知られているように、完全に知るであろう」(コリントⅠ13・9〜12)。
すなわちパウロは、律法や預言者の言葉が不完全で部分的なものであることを十分に自覚していながら、それよりも完全なものが伝えられる「その時」が、イエスの時だとは全然思ってはおらず、イエスの教え(キリスト者は「福音」と呼ぶ)に事実上何の期待も持っていなかったことが、この告白から分かってくるのです。
後述するように、パウロは、イエスは十字架の贖罪のために来臨されたとだけ見、イエスが律法よりも高い教えである「福音」を宣べ伝え、それに基づいて「王」として世を統治するために来られた(ヨハネ18・37)のだとは全く考えていません。そのため、律法を全うするはずの福音には全く何の関心もなく、ただ十字架の贖罪と復活、その後の再臨ということにだけ関心を集中していました。
---
次回は、「パウロによるイエスの福音の軽視」をお届けします。
◆『誤解されたイエスの福音』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ