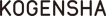スマホで立ち読み 第35弾!
子女の心情と信仰 11
礼拝に行きたがりません
2024.11.04 17:00

スマホで立ち読み Vol.35
『家庭と教会学校で育む 子女の心情と信仰』11
座間保裕・著
スマホで立ち読み第35弾、『家庭と教会学校で育む 子女の心情と信仰』を毎週月曜日(予定)にお届けします。
本書は長年にわたる子女教育の研究と実践の集大成として、家庭教育での父母の在り方についてまとめられた一冊です。
第1部はQ&A形式の提言、第2部は第1部の内容についての理論的な解説がまとめられており、実践と理論の両面で学べます。
※本文中の行事名などは、全て掲載当時の名称です。
---
第1部 小学生期の子女教育Q&A
第1章 家庭での父母による信仰教育
⑩「なんで礼拝に行かないといけないの?」と、行きたがりません。
最近は4年生くらいでも、既に思春期にある子女もいると思います。それまで何の疑問も持たず、親の言うとおりに生きていた子女が、急に納得のいかないことに対して、その意味を確認するようになるのです。いわゆる第2次反抗期です。そのような転換期に来ていると見てよいでしょう。
人の成長は千差万別ですし、単純に肉体の年齢で判断すべきものでもありません。よくよく霊人体の成長を見て対応する必要があります。
神様はアダムとエバが自我に目覚めた時、すなわち学童期から思春期に移行する時、重要な責任分担を提示なさいました。「善悪を知る木の実を取って食べるな。食べると死ぬ」と。それは、神様とアダムとエバの間に交わされた大切な約束事でした。
そのような時、神様はアダムとエバにどのように対していらっしゃったのでしょうか。これまでのように手取り足取りの状態で対応されたのではなく、自らの責任で成長していくことを願われました。
そこには、神様も干渉できない人間の責任分担がありました。人間は自ら動機をもち始め、志を抱いて教育や訓練を受けることで成長します。その時、親は子供の成長を見守り、祈る立場に立ちます。なぜなら、子供が望んでもいないアドバイスはうるさがられるし、反発されるからです。
その時、神様は祈るような思いで、アダムとエバの心情に寄り添っていらっしゃったのです。万が一、アダムとエバが戒めを守れない場合は、ご自分も一緒に地獄に行く覚悟でした。このように、父母は、表面上は子供から離れているようでも、心では今まで以上に子供に寄り添っていきましょう。さらに、子供が自ら動機を発見することができるように祈りましょう。
また、子供自身が直接神様に尋ね求めるように働き掛けることも重要です。神様に尋ね求め、動機を発見していくことが、子供自身の大きな責任分担だからです。礼拝に行くべきかどうかは、「神様に祈って聞いてごらん」と子供に投げ掛け、「神様の答えに従って行動したらいいよ」と言うのです。
このような会話が日常生活の全てにおいて交わされるようになるとよいでしょう。
神様に祈り求める習慣が身につけば、自らの責任分担を果たせる人間に成長するはずです。親や先生のせいにしたり、人のせいにしたりして、自らの責任分担を回避し、責任転嫁しないように、いつも神様に問う習慣を身につけることが大切です。
祈りとは願い事をするためだけのものではなく、神様の声を尋ね求めるものです。それが人間の責任分担であると言っても過言ではありません。
この時、父母としては、子供が神様に尋ね求める以上に、神様に尋ね求める責任分担があります。
そもそも、祝福子女の教育は、人類初めての経験です。ましてや、真(まこと)の家庭理想の実現は、前人未到のもので、開拓にほかなりません。一つ一つ神様に尋ね、答えを頂きながら子女教育の道を開いていくのです。
そして、真の父母という実体がいらっしゃり、全ての問題を解決することのできる「み言(ことば)」があります。み言を探求していけば、必ず答えがあるはずです。
子女自身の責任分担もさることながら、父母の責任分担がどれほど大きいか量り知れません。幼児教育の分野では、既に光の子園が開拓の道を切り開いてきました。先人が開拓してきた、その中にも答えを見いだすことができます。ただし、自らの責任分担を果たしてこそ、その答えに行き着くのであって、尋ね求めていないところに答えはありません。
私たちの歩みは、神様から導かれたという実感の中でなされるべきです。常に「祈り」と「み言」を手に、探求して行く道程です。方便(テクニック)的になったり、人間的な知恵のみで対応しようとしたら、うまくいかないでしょう。
人間の責任分担の核心は、真の愛の人になることですから、子女のために毎日祈りましょう。時として教会学校に行けない日があるとしても、「私の子女は私が責任をもちますから、神様、心配しないでください」と祈り続ける父母になりたいものです。そうする中で、私の中に大きな愛が膨らんでくることでしょう。
そして、大きくなった愛で子女を見つめる時には、また違った愛が膨らむことでしょう。外的な子女教育の成果を求める以上に、内的な愛の成熟という観点で、自分自身も子女も見つめる者になることを目指しましょう。
---
次回は、「『為に生きる』を教える」をお届けします。
◆「一気に読んでしまいたい!」というあなたへ
『家庭と教会学校で育む 子女の心情と信仰』を書籍でご覧になりたいかたは、コチラから