誤解されたイエスの福音 2
「省略されたイエス像」をつくり出したパウロ
2024.10.25 12:00
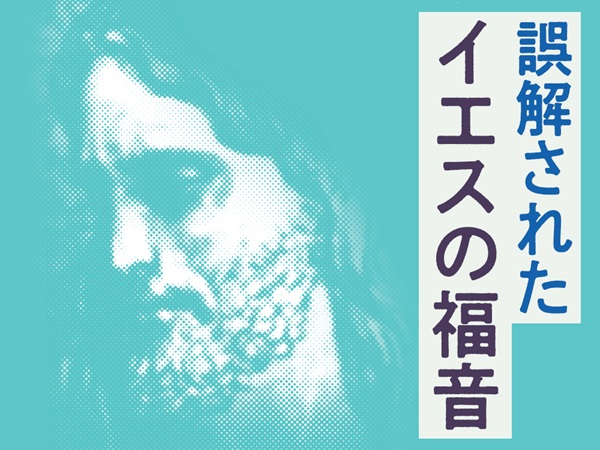
誤解されたイエスの福音 2
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「誤解されたイエスの福音」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
パウロのイエス観は果たして正しかったのか。イエス・キリストの再臨期を迎えた今、聖書の記述をもとに徹底検証します。
野村健二・著
推薦のことば
キリスト教は、「十字架と復活から出発した宗教」と言われます。では、どのようにしてイエスの十字架と復活が、人類における決定的な救済の出来事となり得たのか。そのことを弁証しようとする試みから、キリスト教の神学は構築されてきました。
そのなかで、重要な神学的問いの一つが、人類の罪を贖(あがな)った「ナザレのイエスとはいったい何者なのか」という問題です。既にAD4世紀に、イエスは被造者であるか否かという問題をめぐって、神学論争が展開されていくようになります。
神とイエスは「類似(ホモイウシオス)」と主張したアリウス派と、神とイエスは「同質(ホモウシオス)」と主張したアタナシウス派との間で起こった、いわゆる「三位一体論争」は、やがてAD381年の「ニカイア・コンスタンティノポリス信条」によって、アリウス派の立場が決定的に棄却され、決着しました。
それ以降、キリスト教史において、「すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、造られることなく生まれ、父と一体(ホモウシオス)」と謳(うた)った、アタナシウス派の流れをくむ信条を認めない者は、異端者として断罪されてきたのです。
約半世紀ほど遡(さかのぼ)ったAD325年には、三位一体論争を終結させる目的から、「ニカイア公会議」が開催されました。その会議はコンスタンティヌス大帝によって招集された事実からも明らかなように、極めて政治的色彩の強いものであったと言われています。以後、半世紀にもわたった神学論争では、アリウス派もアタナシウス派も、共に自らの正統性を裏づけるため、聖書から典拠を示し、自説の正しさを主張しようとしたのです。
例えば、アリウス派は、イエスを神に従属させていると思われる聖句(コリントⅠ11章3節、同15章28節、コロサイ1章15節、テモテⅠ6章16節、マルコ福音書10章18節、ヨハネ福音書14章28節、同17章3節など)を示し、一方、アタナシウス派は、ヨハネ福音書1章1〜18節の「ロゴス賛歌」、同10章30節、同14章9節、ロマ書9章5節などを典拠とし、それぞれが主張し合ったのです。
果たして聖書の言葉はどちらの主張を支持していると言い得るのか。政治的陰謀を絡めながら、両陣営の激しい攻防が約半世紀にわたって続きました。いずれにせよ両陣営は自説の正しさの裏付けを、共に聖書に求めていたのです。
ところで、一旦どちらが正統でどちらが異端であるかが決定された問題を、再び蒸し返して論じることは大変勇気の要る行動です。なぜなら異端審問に遭いかねないからです。
しかし、宗教和合の必要性が叫ばれる今日、この三位一体の問題をあえて取り上げる意義は、極めて大きいものがあると言わざるを得ません。なぜなら、イスラームの『クルアーン(コーラン)』は三位一体を明確に否定しており、そのことが、キリスト教世界との軋轢(あつれき)をもたらしてきたためです。今日、世界人口の約3分の1を占めるキリスト教に対し、世界人口の約5分の1を占めるイスラームであるがゆえに、この両者が和合し、世界平和を実現するに当たって、この三位一体の問題解決は避けることのできない課題となっています。
その意味で、本書は、「イエスは神そのものか」というテーマを掲げ、キリスト教神学の根幹と言い得る「三位一体」の問題に対し、果敢に挑戦していると言えるのです。
本書のもう一つのテーマは「イエスの本来の使命」です。
キリスト教は、「イエスは十字架で死ぬために来られた」と信じてきました。すなわち人類の罪を清算するために、神はあらかじめイエスの十字架の死を意図しておられたというのです。いわゆる「十字架贖罪(しょくざい)」の問題です。
そもそも、この十字架贖罪の教えを確立させるために大きな働きをした人物が、使徒パウロでした。キリスト教の出発はパウロにあったと言われるほど、その影響力は絶大です。しかし、イエスの生涯を著した福音書は、すべてパウロ書簡よりのちの時代に編纂(へんさん)されました。したがって、福音書は、十字架贖罪を打ち出したパウロの思想を色濃く反映していると言わざるを得ません。
では、キリスト教に多大な影響を与えたパウロは、生前のイエスについてどのくらいのことを知り得ていたのでしょうか。それが大きな問題です。実は、パウロ自身は、書簡の中で「わたしはイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことは、あなたがたの間では何も知るまいと、決心した」(コリントⅠ2・2)と告白しているのです。
20世紀の著名な神学者ルドルフ・ブルトマンは、自著『イエス』の中で、「私たちはイエスの生涯と人となりについて、ほとんど何も知ることができないと考えている」と述べ、人々を驚かせました。
この「史的イエス」の問題に関して「ほとんど何も知ることができない」という状況は、既にパウロの時代にその源流を求めることができるとも言えます。なぜなら、パウロの宣教以降の時代を生きた福音書記者の関心事は、パウロの影響を受けて、生前のイエスの生きざまよりも「十字架上のイエス」であり、「十字架に向かいたるイエス」を描くことに、意識が集中していたからです。
前掲のコリント人への第一の手紙の言葉に代表されるように、パウロは「省略されたイエス像」をつくり出していたと言い得るのではないでしょうか。
そのような背景をもつパウロ書簡および福音書を土台として、今日、聖書批評学が進展していますが、聖書の言葉の記述そのままを引き合いに出して「イエスの福音の実体」に迫ろうとする試みは、より困難なものとなっています。
以上のような聖書学の実情を踏まえたうえで、あえて「イエスの本来の使命」というテーマを掲げ、史的イエスの問題に果敢に挑戦しておられる著者、統一思想研究院の野村健二氏の勇気に対し、心からの称賛を捧げるものです。
これらキリスト教神学の聖域とも言い得る「三位一体」と「十字架贖罪」の問題に、あえて取り組まれたことに敬意を表するとともに、広く多くの皆様に推薦する次第です。
2011年7月13日
世界基督教統一神霊協会 御言(みことば)研究室
太田朝久
---
次回は、「パウロはイエスをどのように見ていたか」をお届けします。
◆『誤解されたイエスの福音』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ



