日本人のこころ 90
吉田満『戦艦大和ノ最期』
2024.09.22 17:00

日本人のこころ 90
吉田満『戦艦大和ノ最期』
ジャーナリスト 高嶋 久
死に逝く若者の生甲斐は
吉田満(みつる)著『戦艦大和ノ最期』は1945年4月、沖縄に向け出撃した戦艦大和が米軍機の攻撃を受け、徳之島の西北沖で撃沈したとき、たまたま哨戒当直として艦橋にいた21歳の兵科士官・吉田満が、戦艦大和の出撃から沈没までを綴った本で、戦記文学の最高傑作とされるものです。哨戒当直とは、艦内の見張、報告、命令を掌握する役で、戦闘の全容を観察することができました。東大法学部から学徒出陣した吉田は、自分が目の当たりにした戦艦大和の最期を、後知恵ではなく、正確な観察と印象を、あたかも科学的な記録のように書き記しています。

頭部に裂傷を負いながらも死を免れた吉田は45年9月、疎開先の隣に住み、父と親しかった作家・吉川英治の勧めにより、ほぼ1日で漢字とカナによる文語体の「戦艦大和ノ最期」を書き上げたのです。読み始めは、慣れない文体に抵抗感があるのですが、読み進むうちに、なるほど事実の合理的な記述には最適だと感じるようになります。文語体にした理由について吉田は「第一は、死生の体験の重みと余情とが、日常語に乗り難いことであろう。第二は、戦争を、その只中に入って描こうとする場合、“戦い”というものの持つリズムが、この文体の拡張を要求するということであろう」(初版あとがき)と述べています。
吉田の原稿の写本を読んだ小林秀雄が、立派な文学だとして雑誌掲載を依頼してきたのですが、GHQの検閲で不可になり、日の目を見たのは占領終結後の1957年になってからでした。GHQは戦意高揚と読める部分が気に入らなかったのでしょう。
それに対して吉田は、「この作品に私は、戦いの中の自分の姿をそのままに描こうとした。ともかくも第一線の兵科士官であった私が、この程度の血気に燃えていたからといって、別に不思議はない。我々にとって、戦陣の生活、出撃の体験は、この世の限りのものだったからである。若者が、最後の人生に、何とか生甲斐を見出そうと苦しみ、そこに何ものかを肯定しようとあがくことこそ、むしろ自然ではなかろうか」(同)と書いています。
イギリスに学んだ伝統がある海軍では、兵士たちの間で自由な議論が行われていました。例えば、まるで特攻隊のような戦艦大和の無謀な出撃について「無意味だ」とする声が上がったとき、吉田より半年ほど若い大尉は「進歩のない者は決して勝たない。負けて目覚めることが最上の道だ。日本は進歩ということを軽んじすぎた。私的な潔癖や徳義にこだわって、本当の進歩を忘れていた。敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか…俺たちはその先導になるのだ。日本の新生にさきがけて散る。まさに本望じゃないか」と応じています。
吉田と同世代の人から、「死んでいった戦友に申し訳ない」という言葉をよく聞いたことがあります。そんな戦中派の倫理観が、戦後復興を推し進めたとも言えます。ところが、繁栄した日本で日本人はどうなったのでしょうか。
「死者」の視点から今を見る
吉田の生誕100年の昨年に出た貝塚茂樹著『吉田満-身捨つる程の祖国はありや-』(ミネルヴァ書房)は、戦友たちの死の意味を問いながら、日銀社員として戦後復興・経済成長に尽くしてきた戦中派の生涯をたどっています。
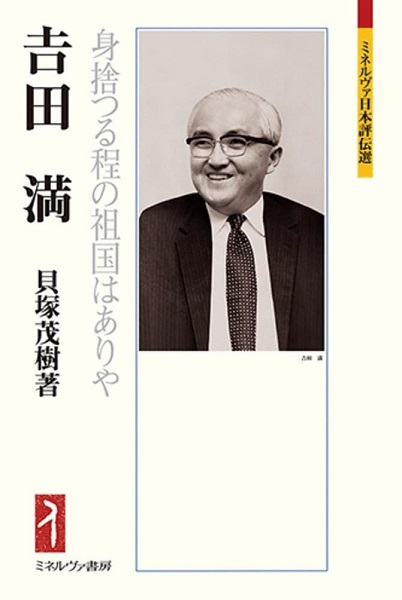
興味深いのは吉田とキリスト教との出会いです。吉田の原稿の写本を見たカトリック神父に招かれて一晩語り明かし、初めて理解されたと感じた吉田は、日銀で有志らと聖書を学ぶようになり、やがて受洗するまでになります。
その後、妻がプロテスタントだったことから牧師との交流が始まり、彼のキリスト者の戦争責任論に啓発され、探求する死生観に神の視点が加わるようになります。いつも抱えている死者への後ろめたさを、信仰としてどうとらえるかを問い求めたのです。
高度経済成長期の1970年代、吉田は戦没学徒の遺書や手記を手がかりに、「公と私」の問題を考えるようになります。例えば「生きるには、ただ単に私に徹するのではなく、この私を真に生かす、真の公がなければならないのではないか…〈私〉というものは、真実な、新しい〈公〉に役立ててこそ、本当の私となるものだからです」と。驚くほど「私」のなかった戦没学徒を思い、過剰な個人主義に疑問を呈し、古くて新しい問題を提起しています。大学で道徳教育を専門にする貝塚教授にとっても大きなテーマなのでしょう。
吉田は「古今東西に比類のない超弩級戦艦の演じた無残な苦闘が、はからずも日本民族の栄光と転落の象徴を形作っている」とし、「それは近代日本が明治以来の躍進の果てに到達した頂点の高さを示すとともに、みずからの手で歴史を打ち建てるのにいかに無力であるかを露呈するものでもあった。科学と技術の粋は非合理きわまる精神主義と同居し、最も崇高なるべきものは最も愚劣なるものの中に埋没することによって、ようやくその存在を許された」と断じています。それは今日の日本にも当てはまるでしょう。
貝塚教授は、「戦没学徒の亡霊が、…いま繁栄の頂点にある日本の街を、さ迷い歩いている」幻覚にとらわれることがあるという吉田の言葉に衝撃を受けたそうです。生者だけでなく、「死者」の視点から、今の社会を見直す必要があります。




