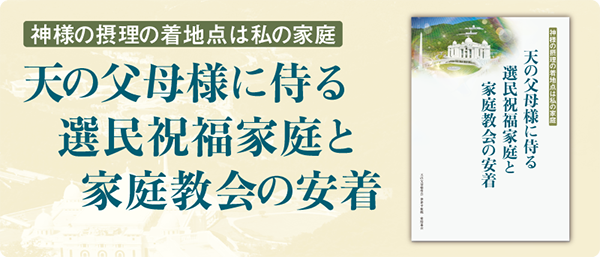レダ摂理 2
日本からの支援を募るため、現地での情報収集に奔走
2025.03.26 17:00

レダ摂理 2
『世界家庭』に掲載された飯野貞夫さんの証しを、毎週水曜日配信(予定)でお届けします。
飯野絢子(あやこ)さんの証しに続き、絢子さんの夫であり、サウジアラビア国家メシヤとして活躍した飯野貞夫・天一国特別巡回師(777家庭)のレダでの歩みを紹介します。(一部、編集部が加筆・修正)

日本からの支援を募るため、現地での情報収集に奔走
私はレダの現地を視察することもなく、直ちに帰国し、すぐ支援のための事務局を開設しました。1年後には、スタッフとして柴沼邦彦さん(モナコ国家メシヤ、777家庭)、戸石文夫さん(ジプチ国家メシヤ、1800家庭)などが入りました。
12月末に、レダから佐藤輝夫さん(エリトリア国家メシヤ、1800家庭)が帰国しました。映りは悪かったものの、現地を撮影したビデオフィルムを持参していました。それは非常に貴重な資料になるとともに、大きな刺激ともなりました。すぐに、さまざまな形で各責任者や教会スタッフに見せました。おぼろげだった現地の大変さが衝撃的に伝えられ、一段と支援に弾みがつきました。
私は、現地の状況をもっと正確に詳しく映像で記録し、苦労の現実を伝えたいと思うようになりました。それは現地メンバーの励みになるとともに、支援の側に立っている国家メシヤたちをも鼓舞、激励することができます。同時に、密使として遣わされたレダ・プロジェクト担当者の開拓の記録として、歴史に残るのです。
そのためには、支援組織の要である事務局長の私が現場を知らないのでは話になりません。早期にレダを訪問し、現状の記録を撮ってこなければならないという思いがつのりました。そしてそれが必ず全体のためになるとの確信もありました。
早速、レダ行きを計画しました。当面は私が持っているしっかりしたカメラで写真をたくさん撮ってくることで、皆に紹介もできるし、記録も残せると考えました。
こうして2000年2月初め、予定どおり一人で日本をたち、30時間かけてアスンシオン(パラグアイ首都)に到着。佐野道准さん(チリ国家メシヤ、1800家庭、スペイン語・英語・フランス語が堪能)の出迎えを受け、さらにセスナ機で2時間ほど飛ぶと、ついにレダに降り立つことができました。
日本の情報やお土産を携えて行ったこともあり、レダのメンバーは大変喜んでくれました。このとき、梶栗玄太郎先生(マケドニア国家メシヤ、43家庭)をはじめ、真っ黒に日焼けした十数人の開拓メンバーと再会しました。数日、宿舎建設の手伝いをしたり、一人一人と交流して心境を確認したり、現地を撮影したりして過ごしました。
台所では栄徳光夫さん(ギリシャ国家メシヤ、777家庭)が、鍋で蛇の料理を作っていました。外部との連絡は、衛星電話が唯一の貴重な命綱で、藤原秀敏さん(クロアチア国家メシヤ、777家庭)がアスンシオンと交信していました。
トイレは外の、ドアのない掘っ立て小屋にあり、しゃがんでします。電気もないので夜は真っ暗で、いつ毒蛇が入って来るか分からず、緊張しました。明かりがないので、夜は星空を満喫できましたが、獣の遠ぼえが時折聞こえ、原野の中にいることを自覚させられました。
小さな発電機で電気を起こし、辛うじて食事や訓読のときは明かりがともるので、助かりました。水は川の茶色い水を、ドラム缶に砂利や砂を入れた濾過(ろか)器でこした後、塩素殺菌をして飲んでいました。冷蔵庫もないので、腐るものは保管できず、暑くても冷たい水や氷はありません。


それでも皆、朝早く訓読会をした後、日中は汗だくで黙々と働きます。皆、当時でもすでに50代、60代ですが、「さすがにみ旨に殉じているなあ」と感服しました。
ちょうど季節は真夏で、手も足も蚊に食われ、かゆくてかきむしると、その傷がうんで真っ赤に腫れ上がりました。夜も暑く、寝苦しいことこの上ありません。それでも皆、毎日の労働で疲れ果てていますから、日本から運んだ蚊取り線香をたき、クーラーのない中でも、いびきをかきながら休んでいます。
真のお父様も日々、朝早くから夜遅くまで灼熱に身をさらし、蚊の大群と闘いながらパラグアイ川などで3年以上、釣りの蕩減(とうげん)条件を立てておられたのだと思うと、全てを感謝していく以外にありません。
滞在中、大場良一さん(アラブ首長国連邦国家メシヤ、1800家庭)の協力で、岸辺での魚釣りに挑戦し、ピラニアやパクーを釣りました。夕方にはコウモリがたくさん飛んでいましたが、川辺に沈みゆく夕陽の美しさには息をのみました。
このときの滞在は2週間ほどでしたが、非常に貴重な体験となりました。そのときに撮った基地や自然の写真の数々は、レダの現場の表情を的確に伝えてくれるものでした。帰国後、これらの写真を使って報告すると、皆大いに刺激を受け、支援金も続々と集まりました。このことから、「次回は、ビデオを撮れたらいいなあ」と思うようになりました。
資金集めの中心は国家メシヤの夫人たちで、大きく貢献してくれました。そこで、2000年5月には、夫人の代表4人を案内してレダに行きました。そのうちの一人、森川五八夫さん(スーダン国家メシヤ、777家庭)の夫人、道子さんは、その後の植林活動などを通して、支援活動の先頭に立ってくれるようになりました。
このとき、夫人たち一行はオリンポのほか、オリンポからパラグアイ川を船で15分ほどの、対岸のブラジル側にあるナビレキにも行きました。ちょうど真のお父様が来られ、ばったり合流。早速、お父様のボート「グッド・ゴー」に乗せていただいて、しばし釣りを満喫しました。またお父様は、「女性の中心者を決めてあげよう」とおっしゃり、4人の中で一番若い高津鈴子さんを立ててくださいました。鈴子さんは、レダで植林活動を推進した高津啓洋さん(エストニア国家メシヤ、777家庭)の夫人です。
こうして一行は、天の導きを感じながら帰国し、その後も継続的に力を合わせて黙々とレダ摂理に走り続けてきました。
私たち夫婦も日本で積極的に支援していましたが、次第にそれだけではいけないと思うようになりました。かつてジャルジン修練会(世界平和と理想家庭のための40日特別修練会)で、私は真のお父様から直接、「飯野、南米に来るんだよ」と言われました。妻も「絢子、日焼けして顔が牛の皮のようになってもいいの?」と言われ、「はい、問題ありません」とお答えしたのです。
このように夫婦共に約束してきたこともあり、支援活動の責任者が身をもって示さなければならないという思いも重なって、2002年と2006年、夫婦で40日滞在して、レダで歩ませていただきました。また2006年以降、私は5年半、妻は4年半レダに滞在して活動することができました。
(続く)
---
次回は、「レダの最初の建物として海軍の警備所を国に奉献」をお届けします。