幸福への「処方箋」28
メシヤのための基台
2024.05.21 22:00
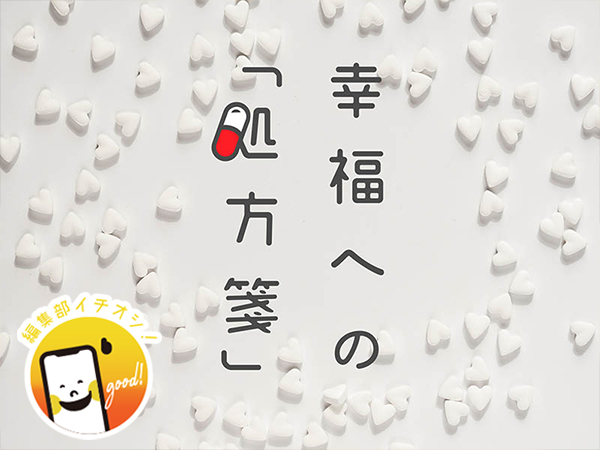
幸福への「処方箋」28
「幸福への『処方箋』」を毎週火曜日配信(予定)でお届けいたします。
野村 健二(統一思想研究院元院長)・著
第五章 堕落性からの脱却
メシヤのための基台
統一原理によれば、現存する全人類は「堕落した父母―アダムとエバの子孫」です。したがって、全人類は一人残らず「堕落性本性」を受け継いでいるため、その堕落性本性の根である原罪を贖(あがな)い、根治するためには、「人類の真(まこと)の父母」として来られるメシヤを迎えて、根本的な蕩減(とうげん)復帰(創造本然の位置と状態への復帰)をしていただかなければなりません。そのためには、「『メシヤのための基台』を完成した基台の上でメシヤを迎え、原罪を取り除かなければならない」(『原理講論』277頁)と統一原理は説きます。
この「メシヤのための基台」は、「信仰基台」と「実体基台」から成り立っています。この二つはもともとアダムが完成するために立てなければならなかった条件でした。
① 信仰基台
アダムはもともと「善悪を知る木からは取って食べてはならない」(創世記2・17)という神のみ言(ことば)を、自分にまかせられた責任分担として一定期間(21数に相当の成長期間)信じて、守り続けなければなりませんでした。これが「信仰基台」です。この信仰の保持によってもはや絶対に堕落しない基準にまで成長することができます。そうなったら、同様に完成実体となったエバと神の祝福を受けて結婚し、子孫を生み殖やしても大丈夫です。「この成長期間は(神の創造原理に従って)数によって決定づけられていくものであるがゆえに、結局この期間は、数を完成する期間であるということもできる」(講論278頁)。
②実体基台
このように、「アダムが神のみ言を信じ、それに従順に従って、その成長期間を完全に全うすることにより『信仰基台』を立てることができたならば、彼はその基台の上で神と一体となり」、同時に、神がアダムをご自身の性質と完全に似せるためにくださるみ言(創造理想)と一体になりたいという願いをこめた「実体基台」を造成することによって、「創造本性を完成した、み言の『完成実体』となり得たはずで」(講論278頁)した。
この「実体基台」という概念は、ヨハネ福音書の冒頭に述べられている思想と一脈相通じるところがあるように思われます。
「初めに言(ことば)があった」(ヨハネ1・1)、すなわち、この宇宙形成の出発点に「言(理想)」があったという物事のとらえ方は、初めにあったのは無、あるいは偶然だというダーウィンの進化論や、マルクスの弁証法的唯物論とは全く相容れない発想です。
「言は神と共にあった。言は神であった」(同1・1)。ここでは、言と共に神の存在が語られています。言は全知全能の神と共にあった。というよりは、言と神とは同じ性質を持っているという思想が語られています。どういう点で同じかというと、神は全知全能であっても、独りでは喜びがない。喜びを感じるためには、自分と同じ知情意を備えた存在が別にあって、その存在に与えたり、受けたりという愛の交わりをすることが必要です。そういう存在を持つためには、それがどういう存在であるかを言で表現し、その言を手がかりにしてそのような存在を具体的に創造しなければなりません。こうして神は言となり、言は第二の神―人間となったというのが統一原理のとらえ方です。
「この言は初めに神と共にあった。すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった」(同1・2〜3)。―それでは、第二の神、人間が一人あればいいかというと、無限の情念をもつ神はそれだけで満足することはできません。無限の数と質の人間が必要であり、無限の数と質の人間を殖やしていくためには肉体が必要であり、肉体を維持するには人間の外にある食物を必要とします。さらに、神が人間という愛の対象が必要であったように、人間にも無限の質と量を持つ愛の対象群が必要です。このように人間の肉体を維持し、人間の愛と喜びの対象となる万物をつくるためにも特定の構想―言が必要であり、そうした言が神につきものとして、神と共にあり、すべてのもの(人間と万物とさらには天使)はこれによってできたと考えなければなりません。このようにとらえると、統一原理の思想とヨハネ福音書の主張とは一致してきます。
「実体基台」とは、その神のみ言の完成実体となることをめざし、人間の側が努力して到達していくことを意味します。
「この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった」(同1・4〜5)。―ここで、この「言」は「命」であり、さらに「光」であるとされ、「やみ」と対比されていきます。このくだりは、創世記の冒頭と照らし合わせてみるとよく理解できるように思われます。
「はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく、むなしく、やみが淵(ふち)のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた」(創世記1・1〜2)
ここで述べられているように、神の天地創造のみわざに当たって、はじめは「形なく」、「やみ」が全面をおおっていました。アダムとエバが堕落した後もそういう「やみ」のただ中にあったといえます。
「神は『光あれ』と言われた。すると光があった」(同1・3)
それと同じように、「み言」の実体であるイエスの登場とともに、光がやみの中にある全人類を照らし出すようになり、「やみはこれに勝たなかった」と先のくだりは読み取れます。
「ここにひとりの人があって、神からつかわされていた。その名をヨハネと言った。この人はあかしのためにきた。光についてあかしをし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ、光についてあかしをするためにきたのである」(ヨハネ1・
6〜8)。
ここでは洗礼ヨハネの使命(ただし統一原理に従えば、その使命が果たされたとはいえない)が、はっきりと規定されています。「彼は光ではなく、光についてあかしをするためにきた」。すなわち、ヨハネは「み言」の実体―メシヤそのものではなく、メシヤであるイエスと堕落人間の橋渡しをする「信仰基台」「実体基台」を造成することがその役目であったというのです。
「すべての人を照らすまことの光があって、世にきた。彼は世にいた。そして、世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた」(同1・9〜10)。
ここには、「世は彼によってできた」とイエスを神と同一視するようなことが書かれていますが、もしそうであったらどうしてイエスは十字架上で「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ27・46)と叫ばれたのでしょう。この叫びは、イエスが神とは別人格であられたことを明示するものだと思われます。イエスは神そのものではなく、神とその知情意の機能においてそっくりに造られた堕落していない人間―真の人間(父母)であられたというのが統一原理の見解です。
「彼は自分のところにきたのに、自分の民は彼を受けいれなかった。しかし、彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである」(ヨハネ1・11〜12)。
ここでは「信仰基台」ばかりが強調されていて、「実体基台」が無視されているようです。信仰だけでは霊的な救いが得られても、個性完成して真の父母となることはできません。これはイエスが十字架上の死によってメシヤとしての使命を完全に果たすことができず、霊的な救いの道を開かれただけにとどまり、完全な使命の達成をメシヤ再臨にまで延期せざるをえなかったことが分からなかったことを示すものだといえます。このことについては、『原理講論』後編、第2章第3節「イエスを中心とする復帰摂理」を参照してください。
「そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った」(同1・14)。
このくだりが「実体基台」の問題とかかわってきます。
アダムは個性完成する前に神のみ言に背いてエバと性関係を結んでしまったために、み言の完成実体となることができませんでしたが、その後4000年にわたっての蕩減復帰の末に、罪を全く負わない白紙の立場に生まれて来られたイエスが、神のみ言を守り通し、歴史上初めて神のみ言どおりの完成実体となられたという事実が、ここには述べられています。
メシヤが現れるまでは、メシヤの代理として、神から与えられたみ言、石板、契約の箱、幕屋、神殿に対して信仰基台、実体基台を造成してきましたが、メシヤが降臨してみ言の完成実体となられてからは、メシヤそのものに向かって信仰基台、実体基台を造成すべき時代に変わります。イエスはその途中でなくなられたため、霊的なメシヤのための基台をつくることしかできませんでしたが、メシヤの再臨以後は、生きた実体のメシヤに向かって信仰基台、実体基台を造成すべき時代となりました。
---
次回は、「堕落性を脱ぐための蕩減条件」をお届けします。




