幸福への「処方箋」23
公益主義
2024.04.16 22:00
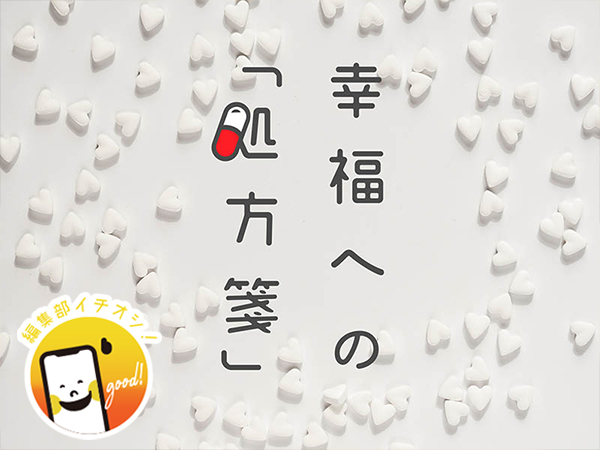
幸福への「処方箋」23
「幸福への『処方箋』」を毎週火曜日配信(予定)でお届けいたします。
野村 健二(統一思想研究院元院長)・著
第四章 真の神主義
公益主義
ところで、普通なら、命を懸けるぐらいに尽くされれば、それに対して恩義を感じ、その恩に報いようとするのが一般的でしょう。しかし、中にはその誠意が通じなかったり、その善意を自分の利益のために利用しようとする人が全くないとは言い切れません。イエスも、「聖なるものを犬にやるな。また真珠を豚に投げてやるな。恐らく彼らはそれらを足で踏みつけ、向きなおってあなたがたにかみついてくるであろう」(マタイ7・6)と言っておられます。
実際、せっかく善意と愛をもって他人に誠意を尽くしても、それが悪用されてかえって全体の不利益になってしまうようではつまりません。つまらないどころか、結果的には、かえって悪の共犯者になってしまうこともあり得ないことではありません。この可能性に対して不注意であることが、宗教家や良心家が往々にして陥る一つの大きな落とし穴だといえます。
ではどうすれば、その善が実際に実のある良き成果をもたらすことができるでしょうか。
そのためには、「他人」のために尽くすことが果たして同時に「全体」の利益となっているかどうかを、賢明に見分けるということが必要です。この全体にとっての善悪は、「私とあなた」という二人の関係だけで決まるものではありません。極端な話、「私とあなたのため」ということで銀行ギャングをやるという場合だってあり得ます。ここであなたがギャングの親分、私が子分であったとしましょう。こういう場合でも「あなた」に誠心誠意尽くすのが果たして社会全体にとって善といえるでしょうか。
確かに、その二人だけにとっては「善」であるかもしれません。しかし、そのために大金を盗まれたり、抵抗すれば射殺するとおどかされる人にとっては、許すべからざる「悪」なのです。
このように、単に「二人」だけにとって「善」であることは、それ以外の者にとっては「悪」であり、したがって、善き成果を上げるためには、「あなた」(ギャングの親分)の利益を考えるだけでは不十分で、「あなた」を含む社会全体にとっての善悪を考えなければならないという結論となります。このような善悪のとらえ方を、利己主義、利他主義に対して公益主義と呼ぶことにしましょう。
それでは、この公益主義に立てば、果たして真に全体のために役立つことができるでしょうか。現実には、国家全体の公益のために役立つと思ってしたことが、実際には役立たなかったという事例が、歴史上これまたいくつもあります。それが例えば「全体主義」と呼ばれるもので、ヒットラーやスターリンの政治がそのよい例です。
これは必ずしも強制されて民衆がそれに従ったものばかりではありません。例えば、スターリンの統治下で強大な影響力を及ぼした、「かろうじて文字が読める程度の教養しか」なかったルイセンコの「学説」がその好適例です(ワトソン、ベリー『DNA』講談社、462頁)。
ルイセンコは「適切な環境を整えてやれば、あらゆる種は別の種に変わることができる」と主張し、それに応じて「すぐさまソビエト全土の熱烈なルイセンコ支持者たちから、種を変えることに成功したという手紙が実験記録とともに送られてきた」といいます。したがってこれは自発的な崇拝感情によって感化されたもので、強制されたものではありません。
彼はまた、苗木は密植すべきであり、「そうすれば苗木は日光や養分を取り合って争うのではなく、共同体の利益のために力を合わせるはずだ」と主張しました。この主張に従って、「1940年末、大勢の農民たちがステップに散開し、樫の木を密植した」。その結果、木々の激しい競争のために、「1956年までにまともに育った樫の木はたった4パーセント、どうにか生き延びたものは15パーセントだった。農業省がいったん承認したルイセンコの植林計画を取りやめたのは、推定10億ルーブル以上が無駄になった後のことだった」といいます。
この「『裸足の教授』はスターリンの死後も、その後継者となったフルシチョフに取り入り、自分はソビエト農業の奇跡を引き起こせる人間だと信じ込ませた」。「ソ連の生物学界はルイセンコの弟子で占められていたため、クレムリンがついに彼を見捨てたのはようやく1964年のことだった」。
このように、主観的には公益のために役立とうとしてやったことでも、そのやり方が非科学的なものであれば、ただ損害を招くばかりだということが分かります。
---
次回は、「神主義」をお届けします。




