日本人のこころ 67
会田雄次『アーロン収容所』
2022.10.09 17:00

日本人のこころ 67
会田雄次『アーロン収容所』
ジャーナリスト 高嶋 久
西欧ヒューマニズムの限界
大学紛争が絶頂期の1968年、学生仲間と京都市で開いた市民講座に、講師として登壇するだけでなく、親身に応援してくださったのが、京都大学人文科学研究所教授の会田雄次先生でした。鴨川の東側、川端通りを少し入った閑静なお宅に伺うと、いつもおいしそうにタバコをくゆらせながら、にこやかに話をされていたのを思い出します。
保守派の論客だった先生は、当時、共産党寄りだった蜷川虎三京都府知事を批判していたのですが、夫人は蜷川知事が中小企業庁時代の部下で、大の蜷川ファン。「家でその話になると、いつも反論されるんだ」と苦笑していました。
会田先生は1916年、京都市の生まれ。父は動物学者で、小さな庭が見える書斎を引き継いでいました。40年に京都帝国大学文学部史学科を卒業し、同大学院に進んでルネサンス史の研究者に。時勢に影響されない分野を探したら、消去法でそこになったそうです。
京大文学部副手から龍谷大学予科講師に転じていた1943年、応召されビルマ戦線に歩兵一等兵として従軍します。そこで、イギリス軍捕虜となり、47年に復員するまでの1年9か月、ラングーンに拘留されました。この時の捕虜体験を基に書かれたのが62年の『アーロン収容所』(中公新書)で、戦後、欧米崇拝に一変した日本人には、目からうろこの鋭いイギリス批判が話題になりました。
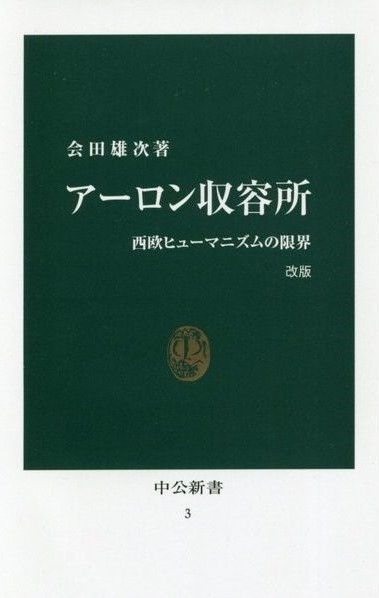
例えば、イギリスの女性兵士は、裸のときに日本人捕虜が部屋の掃除に入っても平気で、下着を脱いで、これも洗えと言ったりする。帰ってきた捕虜は涙を流して悔しがったそうです。そんな振る舞いができるのは、日本人を自分たちと同じ人間とは思っていないからでしょう。
また、砂混じりの米を何とかしてほしいと抗議すると、男性のイギリス兵は不思議そうな顔で、「家畜には問題ないのに」と答えたそうです。会田先生は、大学の同僚や先輩が憧れていたイギリスのヒューマニズムとはこんなものだったのかと思い知らされた、と語っています。
「目には目、歯には歯」がイギリスのやり方の鉄則で、過酷な労働や粗末な食料などを抗議すると、答えはほとんどが「それは日本軍がやったことだ」でした。
西洋史を学んでいた会田先生は、数多くの家畜を飼育してきた西洋と、家で1頭か2頭飼ってきた日本との違いを実感しています。
「私たちは捕虜をつかまえると閉口してしまうのだ。とくに前線で自分たちより数の多い兵隊をつかまえたりしたら、どうしてよいか茫然としてしまうのだ。しかし、ヨーロッパ人はちがう。かれらは多数の家畜の飼育に馴れてきた。植民地人の使用はその技術を洗練させた。何千という捕虜の大群を十数人の兵士で護送していくかれらの姿には、まさに羊や牛の大群をひきいていく特殊な感覚と技術を身につけた牧羊者の動作が見られる。日本にはそんなことのできるものはほとんどいないのだ」
体験に基づく西欧人との比較日本人論の始まりでした。
高校世界史の教科書作り
何とか無事に帰国し、戦争という4年の空白の後に京大西洋史の研究室に戻った会田先生は、今の神戸大学に就職し、妻の祐子さんと結婚、「内職でも何でもやって生きてやろう」という気になります。
そんな時、京大人文研の友人から誘われたのが、高校の歴史教科書作り。占領軍による教育制度改革で、西洋と東洋に分けて教えていたのをアメリカと同じ世界史に統一するので、それを一緒にやろうというのです。学問的に成立するかどうか議論する時間もなく、仲間と相談しながら、インド史と中国史を時代ごとに交互に書き分け、これまで無視してきた西アジアも視野に入れ、ヨーロッパ史と交互に書き合わせるようにしました。
昭和30年代まで日本の学界はマルクス主義一辺倒で、歴史学では東大西洋経済史の大塚久雄の全盛期。唯物史観に基づく大塚史観が圧倒的な信奉者を得ていました。
「現地人など人間扱いしない英国のキリスト教的国家を戦後日本の範とすべき理想国だとする大塚史学に猛反発したが、この大勢の中では、それはゴマメの歯ぎしりに近い。一方、桑原武夫先生流の近代化主義も困る。大きくいうとマルキシズム嫌い、キリスト教嫌い、進歩派嫌い、アメリカ嫌いなのだ。当然、孤立無援といったことになる」(『たどり来し道』新潮社)
昭和43年、東大の林健太郎教授の呼びかけで、田中美知太郎京大名誉教授を理事長に、福田恒存、小林秀雄らと文化会議を結成し、左翼万能の世に鬱積していた多くの学者、知識人を集めることに成功します。
また、国民に直接話しかけるのが一番と、関西テレビのモーニング・ショーにも出演し、人気を博するようになります。その番組に薬師寺の高田好胤師を引っ張り出したのも先生で、写経運動による薬師寺再建の大きな助けとなりました。
先生69歳の文章に「人生の本番だと毎日を楽しんでいる。45歳までを滑走期、それからを上昇期とすれば、今空中遊泳期といえよう。なぜ楽しいかといえば、第一にはつらい拘束から自由になったということだろう」とあります。定年退職したときの解放感は何とも言い難いものだったそうです。今の私も、そんな老後を生きています。




